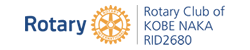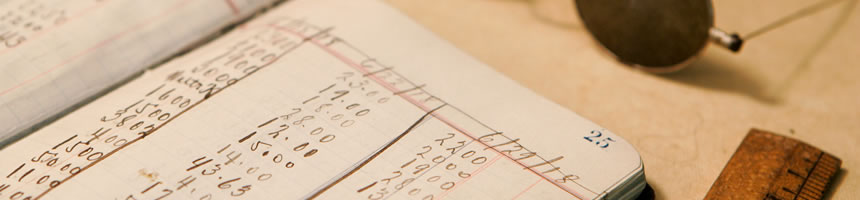
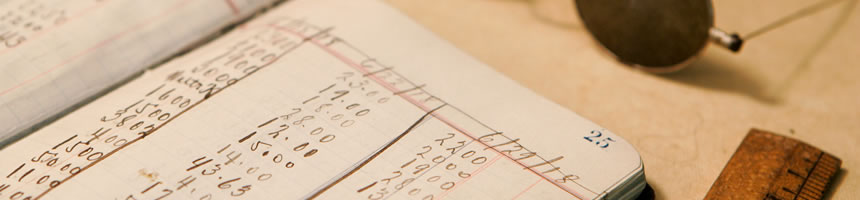
No.24 2014年1月15日号
今週の内容
☆2014年1月21日(火) 第1011回例会
「 豆の話 」
当番 角田 光隆 会員
次週予定
☆2014年1月28日(火) 第1012回例会
「 IM準備のための説明会 」
当番 IM実行委員会
前週の報告①
☆2014年1月14日(火) 第1010回例会
「 フォークリフトとマテハン(物流)の進化が産業発展に 」
当番 岩野 昭 会員
司 会 佐々木 仁朗 SAA
点 鐘 河村 公逸 会長
前週の報告②
お客様紹介
親睦委員会 里見 剛 会員
会長ゲスト
山中 英彦 さん
RCソング
「 たきび 」
BGM
「 When A Man Loves A Woman 」
「 If We Hold On Together 」
「 追憶 」
ピアノ演奏:森田 純子 先生
会長報告
河村 公逸 会長
皆さん今晩わ! 新年を迎え早2週間が過ぎようとしております。皆様、お変わりございませんか?ゲストの皆さんようこそお越しくださいました。本日は、入会の申込みを頂いております 山中英彦様に会長ゲストとしてお越し頂いております。ごゆるりとお過ごし下さい! さて、今月はロータリー理解推進月間です。我がクラブはベテラン会員も沢山いらっしゃいます。ロータリーについて、良くご存知と思いますが・・・ 月間に因んでもう一度、入会の浅い会員の皆様と同様に最近のロータリーに関して、改めてご理解頂くのも一考かと思います。特に、毎月お手元に届いておりますガバナー月信には近々の行事や話題が掲載されております。冊子に関しましては、文字が小さく,見辛いとの声もございますが・・・ 老眼鏡もよし、インターネットのデジタルページでご覧いただく際は、文字が大きく拡大もできます。是非、ご覧ください。又、地区大会が3月に開会されます。今月号の月信に掲載されています様に・・・ 今回に地区大会は竹中平蔵氏の記念講演や、宝塚歌劇記念イベント、JAZZコンサート等もあるようです。ロータリーのホームページをご覧いただき、ご確認ください。是非、ご参加されます様、宜しくお願いします。
月間を機に、地区と我がクラブのホームページを出来れば週に1度開き、情報を取得する習慣を付けてください!ロータリーの行事日程、地区委員会の動きなど概ね見えて来ると思います。
◎週報にURLを記載させて頂きます。
神戸中ロータリークラブ http://www.kobenaka-rotary.com/
国際ロータリー2680地区 http://www.ri2680.org/
マイロータリー https://www.rotary.org/
幹事報告
中橋 康行 幹事・本日例会終了後臨時理事会を行います。
・3月2日地区大会の出欠をFAXで確認しますので返事をおねがいします。
卓話
「 フォークリフトとマテハン(物流)の進化が産業発展に 」当番 岩野 昭 会員
私が物流機器の販売、メンテナンスの業界に入りまして、約40年になります。
本日は昭和の日本産業界が発展してきた事はマテハン業界の進化について話を致します。
今回の卓話資料はオークラ輸送機株式会社 現、代表取締役会長 大庫 典雄様が平成10年9月に発刊された「マテハン昭和史」を参考にしています。
御存じの方もおられると思いますが、大庫会長は日本のマテハン業界で大きな功績を残され、現在も今なお牽引されておられます。
私は日本産業界の発展はマテハンの進化が供与していると確信しています。
マテハンとはMATERIALS HANDLINGを重ねて日本で作られた用語で、物流・運搬を表わしています。第2次世界大戦までのマテハンには「汗・血・涙」の3文字が見えます。
1つ目は、人力荷役・運搬作業での汗であり。人間輸送機としての汗で有ります。
2つ目は、戦乱中での工場、倉庫、輸送での安全欠落での災害で流した血で有ります。
3つ目は荷役、運搬機械の開発、創意工夫の積み重ね、失敗の中で勝ち取った先人たちの
喜びの涙である。汗・血・涙はあらたな形に変わり産業経済の発展を生んで来ました。
我が国のマテハン機械は今や世界一で、ハード・ソフトの両面を世界に送り出しています。
移動の3原則について説明いたします。梃子での起こす、ずらす・コロ敷いての移動、
コロ板での傾斜移動が移動の3原則です。
古代文明にも移動の3原則が見えます。巨石を切り出す時にもテコで起こし、ずらす、
傾斜を利用しての移動、平地ではコロを入れての移動など、3原則が見えるのです。
運びにも原点があります。若い会員は見た事が無いでしょうが、
天秤棒を使って物を運ぶ、我々の幼少時代には良く見慣れた光景であります。
天秤棒の両端に籠や樽を吊るして肩に担ぎ器用に運んでいる。何でもない様であるが
両端に吊るされた物は重さに違いが当然有ります。旨く運ぶコツは天秤棒を担ぐ位置で、肩を支点として両端のバランスをとって担ぐのがコツです。
背負子、赤子を背に家事をする母や、山から薪を運んでいる姿、背負子は両手が自由に
使える利点がある。修羅は雪国での物運ぶソリを想像して下さい。ソリは雪の上だけで無く、雪の無い所でも引いて運べます。修羅に車輪を付けて大八車やリヤカーなりました。担ぐ、引っ張る、これが運びの原点であります。
移動、運びの原点が見える荷役作業があります。それは天狗取り荷役と呼ぶ荷役作業です。
写真は天狗取り荷役作業で本船に石炭を積み込む光景です。
バイスケ(竹製のバスケット)に石炭を入れ、リレー方式で積み込む「人間バケットコンベヤ」である。これは北九州での光景であり、欧米にも荷役風景が紹介されています。
「花と竜」小説や映画でこの光景が描写されている。2社の沖仲士が石炭の積み込みを面子にかけ競争する場面であります。ちなみに天狗取り荷役は手探り荷役がなまって、天狗取り荷役と呼ばれたようです。
この天狗取り荷役もコンベヤの出現で衰退して行く。コンベヤの出現は1919年で米国のステフェンス・アダムソン社が下関の荷役会社と北海道炭鉱汽船会社に納入しています。
ポータブルコンベヤで全長7m、ベルト幅460mm、3馬力のモーターが小型アングルのフレーム上に取付けられ、ローラーチェーンをギヤで減速されていました。只、トラブル続出だったようです。
日本でのコンベヤ開発は1959年頃に樺島小三郎氏が開発しています。樺島小三郎氏はアダムソン社製のコンベヤを試運転から実用化までの責任者であり、北海道室蘭港の北海道炭鉱汽船者の石炭荷役の改善も担当し、当時のコンベヤの欠点を分析し、毎時50Ton搬送能力のポータブルコンベヤを開発、数十台を室蘭港貯炭場に納入しています。当時、室蘭港の石炭荷役は北九州と同じく数百名の作業員が天狗取り荷役をしていたそうで、コンベヤ搬送が軌道にのると、この数百人の雇用が必要無くなっていく事も心配していたとの記述が残っています。その後、毎時200Tonの定置式コンベヤを開発し室蘭港に設置しています。すなわち、コンベヤは石炭荷役から誕生したのである。
フォークリフトの開発は米国クラーク社。1932年バッテリー式立運転型リフトを開発している。1933年にはトウモーター社が現在のフォークリフトの原型であるフォークリフトを開発しています。
日本でのフォークリフト開発は1939年、創立わずか2年の日本輸送機であります。
当時、八幡製鉄所に3Tonのフォークリフト2台を納入、寿命後は高炉で鉄とされている。
開発には八幡製鉄所が入手した米国エール社の写真数枚を参考に製作されたそうです。
名称は腕昇降傾斜型蓄電池運搬車とされています。戦時中の事で英語が使えなかったからでしょう。欧米や日本でのフォークリフトはエンジン式よりバッテリー式が早く開発されています。戦争で石油が不足で有ったからだろうと言われています。
この頃のフォークリフトは現在のようにパレットで運ぶ構造ではなく、コイル等をラムと言う装置でコイルを串差しして運ぶものである。
そして終戦から20年間のマテハンは耐・創・喜が表現できます。
耐は戦後の空襲での運搬機の焼失、空腹に耐えての人力での物の運搬。
創は米国に追いつけ、追い越せの創意、工夫、そして搬送機開発のマテハン業界。
喜びは国民所得倍増論の高度成長期の中、企業が合理化を求め、物流システムが構築され、企業が躍進した喜びである。
国産のエンジンフォークリフトは1949年に東洋運搬機が開発している。東洋運搬機の
創設者は丹羽 昇氏である。丹羽氏は東洋ベアリング製造の社長であったが占領軍の命令による公職追放で解職される。丹羽氏が東洋運搬機を創設した動機は追放2日目に個人的親交のあった米第八軍兵站部のクック大佐との出会いである。東洋ベアリング製造の
武庫川工場が駐留軍の駐屯施設として接収した際、丹羽氏は自ら社長として現場に立ち会い、堂々と工場の引き渡しをおこなった。この時クック大佐と出会ったのである。工場の
維持管理が優れていた事に好感をもたれ、占領軍のフォークリフト整備事業を任されたのである。丹羽氏はフォークリフトの将来性を感じたであろう。
私財100万円を投じてメンテナンス、オペレーション社を立ち上げたのである。
後の東洋運搬機である。
丹羽氏はフォークリフト製作図を米国に貸与を願ったが当然の事、叶わなかった。
そこで神戸港でパレチゼーション作業を行っていたペプシコーラ社に目をつけた。
ペプシ社のフォークリフト修理を無償で行い、OHを瞑目に20日間の条件でフォークリフトを引き上げて全部品をスケッチしたのである。
1949年には国産初のガソリン式フォークリフトを作り上げ、神戸海運局に積載量6000ポンドフォークリフトを4台納入した。この初代機は現在も東洋運搬機(現 ユニキャリア)の工場に展示されている。その後はフォークリフトメーカー10社が続々誕生
(1952年)していますが、主にバッテリー式フォークリフトの開発製造であります。
パレチゼーションはフォークリフトの開発で大きく進歩していく。パレチゼーションとは
パレット荷役の事で産業発展につながっている。1951年、日本でパレット規格化について最初に取り組んだのは東洋運搬機、当時副社長の清水氏である。世界で初めてパレットの規格化に取り組んだのはスエーデンで1949年の事であった。清水氏はパレットの規格化を決定するには鉄道貨車、トラックの床面積を考慮すべきと唱えている。
1957年頃にはフォークリフトの国内使用台数も5000台前後となり、使用するパレットは数百種類となりパレットの標準規格化の機運も動きだし専門委員会を設けパレットの規格原案作成の案を練ることになった。しかし現在のJISパレットT11型は殆んど無視され欧米のT12が主軸となっていた。これは当時の委員会が日本の実態に関する知識が
乏しく、欧米のパレット規格に準拠することに努めたからである。T11型パレットが一貫輸送用パレットとなるには20年を費やしている。T11型とは1100㎜×1100㎜、T12型は片方寸法が1200㎜のパレット寸法である。これら2種類のパレット寸法は現在も天下を二分している。
リーチ式フォークリフトの誕生は1958年である。当時、日本通運は国鉄の後援を得て産業界に鉄道とトラックの共同化による一貫パレチゼーションによる輸送近代化を提唱している。狭い鉄道貨車の積み込み、プラットホームでのパレット作業の出来るフォークリフトの共同開発を各フォークリフトメーカーに依頼、要請に応えたのが日本輸送機である。そして開発されたのが「プラッター」。
かまぼこ型の狭いプラットホームで作業出来るフォークリフトでプラッターの名称となった。小回りの出来るリーチフォークリフトは狭い日本で急速に販売台数が伸び、
各フォークリフトメーカーもこぞって参戦してきた。時間が参りましたので続きは又の機会に。
御静聴有難うございました。
出席報告
☆出席委員会 委員長 紀伊國谷 隆 会員
12月21日 30名 ( 7名MAKEUP)( 2名出席免除) 37/37 100.0%
1月 7日 35名 ( 0名MAKEUP)( 1名出席免除) 35/38 92.11%
1月14日 26名 ( 0名MAKEUP)( 1名出席免除) 26/38 68.42%
委員会報告
その他の報告
ニコニコ箱
☆山田 恵子 副SAA
山中 英彦さん 昨年12月まで篠山クラブでお世話になっておりました。
現在、保守系無所属の山中です。よろしくお願い致します。
岩﨑 さん 山中さん 中クラブへようこそ!!
佐々木 さん 山中さん ようこそ
吉井 さん 三木ゴルフの月例会で、優勝しました。
吉田さん 中橋さんありがとう。
河村 さん 山中英彦様 ようこそ! 宜しくお願いします!
中橋 さん 吉井さん 優勝おめでとうございます。
橋本 さん 山中さんお待ちしておりました。ごゆっくりしていって下さい。
岡田 さん 押部さん おかえりなさい。今年も宜しく。
岩野 さん 本日卓話です。よろしく
大谷 さん 押部さんお久しぶりです。完治するまでお気をつけて。
押部 さん 久しぶりに例会に復帰できてよかったです。
長い間休んで申し訳ありませんでした。
里見 さん 押部さん おかえりなさい。
早く眼がよくなりますようにお祈りしております。
山田 さん 山中さんようこそお越下さいました。押部さん お久しぶりです!
例会予定
1月28日(火) 第1012回例会 「 IM準備のための説明会 」
当番 IM実行委員会
2月 2日(日) 第1013回例会 移動例会「 神戸第2グループIM 」
当番 RID2680地区神戸第2グループ
ガバナー補佐 宇尾 好博 会員
RID2680地区神戸第2グループ IM実行員会
2月 4日(火) 2月2日(日)に移動例会
2月11日(火) 休 日
2月18日(火) 第1014回例会 「 ラウンドテーブルミーティング 」
当番 ロータリー情報委員会
本日のRCソング・BGM
RCソング
「 春よ来い 」
BGM
「 Gelsomina 」
「 Never On Sunday 」
「 Moon River 」
岩野 昭
akira_iwano2@aloha.zaq.jp