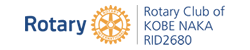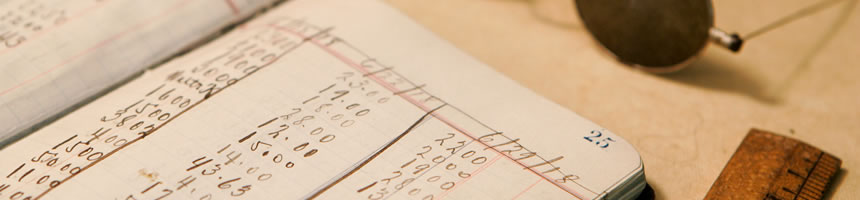
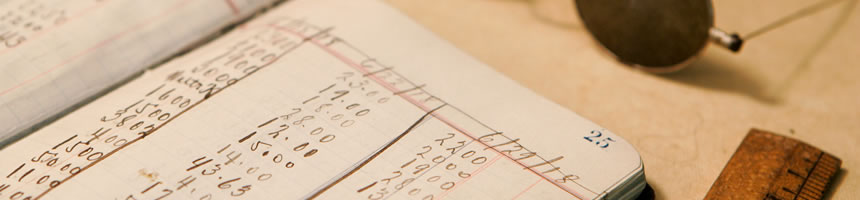
No.06 2019年8月21日号
今週の内容
☆2019年8月27日(火) 1260回
「基本的教育と識字率月間に因んで」
当番 社会奉仕委員長 橋本 猛央 会員
次週予定
☆2019年9月3日(火) 1261回
「MMT」
当番 紀伊國谷 隆 会員
前週の報告①
☆2019年8月20日(火) 1259回
「改正相続法について」
当番 茂木立 仁 会員
司会 吉井 邦弘 SAA
点鐘 岩野 昭 会長
乾杯 吉田 泰弘 副会長
前週の報告②
RCソング
ソングリーダー 親睦活動委員長 山中英彦 会員
「君が代」「われらが生業」
BGMピアノ伴奏 森田純子さん
「好きにならずにいられない」
「嘘は罪」
「魅惑のワルツ」
会長報告
☆岩野 昭 会長
昨夜は秋雨前線の影響で雨が降り、久しぶりの涼しい夜を過ごされたと思います。8月6日は納涼会員家族移動例会で京都高尾のもみじ屋に会員、会員ファミリー、米山奨学生のダンティ・タオさん、事務局の髙橋さん、総勢19名で行ってきました。
連日35℃の猛暑日でしたので京都高尾の気温はかなり違うのではと期待して行きましたが、期待に反して暑かったです。数年前に納涼移動例会で行った時は蛍の見られる時期でしたので非常に涼しかったと記憶があります。
約2時間の床で楽しく過ごして来ました。親睦活動委員会の山中委員長をはじめ委員会の皆様、お世話になりました。
皆様はお盆休みを如何過ごされましたでしょうか?
私は例年のごとく11日から15日までと17日の計6日間は仕事で、9連休の方を羨ましく思いました。15日は神戸市も10カ所位で精霊流しを行なっているようですが
三木市では23カ所で精霊流しを行なっています。私は三木市保健衛生推進協議会の副会長を長年務めている為、毎年地元の精霊流しの会場設営を炎天下、行なっています。
今年は台風10号接近の為に前夜、市役所に召集され中止となりました。
この暑さの中で昼から準備をする必要が有りますのでホットした事は事実です。
18日は初盆を迎えられた所の供物を預る奉仕が急遽決まり、暑さの残る16時から18時まで奉仕活動を行ないました。只、17時を過ぎると涼しい風が吹き、少しずつ秋に向かっているなと感じました。
しかし、まだまだ日中は残暑が続くと思いますので皆様、御身体を御自愛されますように。
早くツクツクボーシの鳴き声を聞きたいですね。
私事ですが会長報告に代えさせて頂きます。
幹事報告
☆松本 考史 幹事・先日の堀田初代会長を偲ぶ会に、クラブより弔電をお送りしました。これに対し、実行委員長から岩野会長宛にお礼状が届いております。
・「ほろにが会の御礼」が神戸ロータリークラブ道満会長よりクラブ宛に届いております。
・2019年1月から6月にロータリー財団に寄付された方へ、確定申告用の領収証が届いております。該当の方にはポスティングしていますので、忘れずお持ち帰りください。
・2018-19年度地区増強拡大委員長より、同年度入会者宛に、「2018-2019年 新会員同期会 世話人会開催・世話人募集のご案内」が届いております。ご興味のある方は、8月22日(木)16時開催の「第1回世話人会」にぜひご参加くださいとのことです。
・地区より、下記のご案内が届いております。
【地区補助金プロジェクト見学】
実施クラブ:相生ロータリークラブ
プロジェクト名:子供の屋外遊び場設置のためのワークショップ
実施日時:講演会 2019年9月8日(日) 13:00~16:30
プレーパーク 同9月29日(日) 10:30~14:00
講演会演題:「なぜ、今、プレーパーク?」
講師 にしのみや遊び場つくろう会代表
日本冒険遊び場づくり協会地域運営委員
災害支援委員会員委員
米山 清美氏
実施場所:講演会 相生市文化会館1階中ホール
プレーパーク 相生市立図書館横の芝生広場(中央公園内)
参加費無料、人数制限なし、軽装でお越しください。
問い合わせ先:相生RC 事務局 電話0791-23-0144
office@aioi.ri2680.org
登録締切日:2019年9月2日(月) ご興味のある方は事務局までお申し出ください。
【ポリオセミナー】
日時:2019年10月14日(月・祝)
第1部 13:00~14:30
講 演「ポリオ根絶へのラストスパートを」
講師:松本祐二第3地域ポリオ根絶地域コーディネーター
第2部 14:30~15:30
講 演「ポリオ根絶の歩みとこれからの取り組み」
講師:ポリオプラス小委員会委員
場所:神戸ポートピアホテル本館B1 和楽の間
出席者:ロータリー財団委員会中心に各クラブ2名
出席頂きたい方へは直接お声がけ致します。
【2019-2020年度 アクトの日】
日時:2019年9月8日(日)13:00~16:30
内容:献血活動、献血呼びかけ運動、ティッシュ配り等
会場:プレンティ西神中央 中央広場
登録料:ロータリアン1,000円(当日現金払い)
ご興味のある方は事務局までお申し出ください。
・7月30日付で、鷲見会員より退会届が提出されましたので、お知らせします。理事会において受理する方向で進んでおります。
・奥田会員が入院されてましたので、慶弔等に関する内規に基づき、後ほど会長よりお見舞金をお渡しいただきます。
卓話
「改正相続法について」会員卓話 担当 茂木立 仁会員
相続法改正のポイント
相続法が大幅改正され、順次施行されています。
親や親族が亡くなる場合もあり、相続は身近な問題です。
相続法の改正のポイントは8個あり、わかりやすく説明します。
「改正ポイント1」 配偶者居住権の保護
「改正ポイント2」 特別受益の持戻し免除の意思表示の推定
「改正ポイント3」 預貯金の仮払い制度
「改正ポイント4」 自筆証書遺言の方式の緩和
「改正ポイント5」 自筆証書遺言の自己保管が不要
「改正ポイント6」 遺留分制度の見直し
「改正ポイント7」 相続の効力等に関する見直し
「改正ポイント8」 相続人以外の者の貢献を考慮
各ポイントについて説明します。
「改正ポイント1 配偶者居住権の保護」について
相続が開始し、被相続人が所有している不動産も他の財産と同様に相続人間で配分していましたが、不動産が売却されるなどし、配偶者が居住先をなくすという問題が指摘されていました。
今回の改正により、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という2つの権利が新設され、配偶者の居住を守ることができるようになりました。
不動者の所有権は別の相続人に移るものの、配偶者は「配偶者居住権」で引き続き生涯無償で家に住むことができ、不動産を所有した相続人は、負担付き所有権を相続することとなります。
ただし、この配偶者居住権は遺産分割協議、遺贈、審判などで認められる必要があり、不動産に関する権利として登記することもできます。
「配偶者短期居住権」とは配偶者は相続開始から6か月間は無償で居住することができ、その間の居住権が保護される権利のことです。
「配偶者居住権」及び「配偶者短期居住権」は2020年4月1日施行です。
「改正ポイント2 特別受益の持戻し免除の意思表示の推定」について
被相続人が生前に特定の人物(相続開始時に相続人となる人物)にだけ偏った贈与(例えば、相続人の1人だけ大学入学資金や教育資金を援助するなど)していた場合、相続開始時に生前贈与分は特別受益とみなされ、相続財産に持戻して計算されていました。
「特別受益の持戻し免除の意思表示」とは、被相続人から遺言等で「特別受益の持戻し計算はしなくていい」との意思表示があれば、遺産分割時に持ち戻し計算をする必要がなくなるという規定です。
結果、生前贈与を受けていた相続人としては、多くの相続財産を受け取れることになります。
例えば、被相続人が居住用の不動産を妻に生前贈与していた場合に持戻し免除の意思表示をしていないと相続発生時に不動産を特別受益として計算されるため、妻の相続できる財産が少なくなってしまいます。
配偶者保護のため、改正法では次のように見直されることになりました。
特別受益の持ち戻しを免除するためには被相続人の意思表示が必要ですが、一定の要件を満たした配偶者相続人については、持戻し免除の意思表示があったと推定され、配偶者相続人が保護されることになりました。
免除の意思表示推定のための要件として
1.婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が、他方に対し、
2.居住用の建物やその敷地を贈与(遺贈)した場合には、
3.持ち戻し免除の意思表示があったものと推定される
これらの要件を満たせば、夫婦間で居住用不動産を贈与した場合、遺言等で意思表示しなくても持戻し計算の免除を免除されることとなり、配偶者相続人に有利な遺産の承継の実現が可能となりました。
施行日は2019年7月1日です。
「改正ポイント3 預貯金の仮払い制度」について
相続開始と同時に預貯金口座が凍結され、引き出しができなくなります。
葬儀費用や病院・施設への支払いにおいて、被相続人の預貯金が使用できず困るケースが考えられます。
相続人間で遺産分割協議が速やかに行われる場合は問題ありませんが、相続トラブルなどがある場合は支払いが滞るなど問題視されてきました。
「預貯金の仮払い制度」により、遺産分割協議前でも家庭裁判所の関与がなくとも、単独で一定額の預貯金の引き出しができるようになりました。
各相続人が引き出せる一定額の算出方法は
相続開始時の預貯金額×3分の1×共同相続人の法定相続分となります。
施行日は2019年7月1日です。
「改正ポイント4 自筆証書遺言の方式の緩和」について
自筆証書遺言は従来においては「全文の自署」が必須条件となっていました。
改正により、遺言書本文は自署が必要ですが、財産目録は自署でなくても可能となりました。
例えば、
財産目録(遺産の明細)をパソコンで作成する
不動産の登記事項証明書の添付でも構わない
預貯金の通帳の口座番号等が記載さいれているもののコピーでも構わない
となりましたが、それぞれに自署と捺印は必要となります。
財産目録の作成が緩和され、自筆証書遺言の作成労力が軽減されることになりました。
施行日は2019年1月13日です。
「改正ポイント5 自筆証書遺言の自己保管が不要」について
自筆証書遺言書は自宅で保管しなくてはならず、滅失や紛失、又は隠匿や改ざんの恐れがありました。
その上、自筆証書遺言書は相続開始時に家庭裁判所で確かに被相続人が書いたものであるという検認の手続きを取らなくてはなりませんでした。
検認手続きは、申立書や必要書類の準備、家庭裁判所への出廷などが必要で、手続きにも時間を要すためなかなか相続手続きが進まない等の問題がありました。
今回の改正により、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらうことができるようになりました。
生前に作成し、法務局で保管してもらうため紛失や改ざん等のリスクもないばかりか、家庭裁判所でも検認手続きが不要となりました。
法務局への持ち込みは遺言者本人が行ない、その場で本人確認も行われます。
閲覧も内容変更も本人の申し出により、本人出頭で行うことができます。
相続人や遺言書に受遺者と記載された者またはその相続人、遺言書で遺言執行者として指定された者は、相続が開始した時から遺言書に関する情報がまとめられた「遺言書情報証明書」の交付を請求することができます。
施行日は2020年7月10日です。
自筆証書遺言の方式の緩和と保管制度の創設にタイムラグがあるのでご注意ください。
「改正ポイント6 遺留分制度の見直し」について
改正により大きく2点が変わりました。
1つめに、遺留分請求権が目的物の返還請求権から金銭の支払請求権となったこと。
2つめに、遺留分の算定方法が明確化されたことです。
遺留分とは一定の範囲の法定相続人に最低限保証された遺産に対する権利のことです。
例えば、兄弟3人が相続人とする遺言書で不動産・会社の株・預貯金のうち会社の株は全て長男に相続させると指定されていた場合、二男三男は法律で決められた遺留分相当額まで長男に請求する権利を行使することができます。
この権利行使を遺留分減殺請求といい、改正前までの相続法ではこの権利行使は目的物の返還請求とされていたため、長男(受益者)は会社の株式を返還し、二男三男(遺留分権利者)を含む3兄弟で共有状態となり事業継承が円滑に行われないという事態が発生していました。
改正により、二男三男(遺留分権利者)の遺留分減殺請求権は守られ、長男(受益者)も返還しなくてはなりませんが、目的物である株式自体を返還する必要はなく、金銭の支払いとなり、目的物が共有されるという問題が解決されました。
請求権の内容変更に伴い、遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へと変更されました。
遺留分の算定方法ですが、従来の法続報では、相続人が被相続人から生前に受けた贈与などの特別受益は何十年前のものでも遺留分額の算定に含めて計算されていました。
改正により、「相続開始前10年間にしたものに限る」と変更になりました。
遺留分については、過去の特別受益をどこまで遺留分の算定に含めるかが争点となることが多かったため、10年と区切ることで遺留分侵害額の予測がしやすくなり、基準も明確になり早期解決の一因になると考えられています。
「改正ポイント7 相続の効力等に関する見直し」について
相続の効力等に関する見直しについては、大きく2点が挙げられます。
まず1点目は、権利取得の対抗要件の見直し、2点目が相続債権者の立場の明確化です。
権利取得の対抗要件の見直しとは、法定相続分を超える権利を相続した者は、取得に至った原因(遺言、遺産分割協議等)に関わらず、法定相続分を超える部分について、第三者に権利を主張する(対抗)には、登記や登録などの手続きをしなくてはならないということになりました。
例えば、相続人が姉妹の2人で、被相続人が不動産を全て姉に相続させると遺言した場合、妹が遺言書の存在を知っていながら、自分の法定相続分による登記を済ませ売却しても、姉は自分の法定相続分を超える部分(妹が売却した持分2分の1)について第三者に権利取得を対抗できません。
妹が登記する前に先に登記を済ませないと妹が売却しても何も対抗できないということになります。
相続債権者の立場の明確化についてですが、被相続人が負債を抱えて亡くなった場合の負債の返還を請求する権利がある人を相続債権者といいます。
相続債権者は、相続分の指定がされた場合でも相続指定分に縛られることなく、各相続人に法定相続分に応じて請求できると明文化されました。
ただし、相続債権者が指定された相続分に応じた債務(負債)の承継を承認した場合はこの限りではありません。
例えば、妻子の2人を相続人として預貯金と300万円の負債を残して被相続人が死亡し、妻に1、子に2の分配だった場合、相続債権者は指定相続分として妻に100万円、子に200万円を請求することができ、または法定相続分として妻に150万円、子に150万円を請求することもできるのです。
債権者が法定相続分と指定相続分のどちらに沿って請求するのかを選択することができるのです。
施行は2019年7月1日です。
「改正ポイント8 相続人以外の者の貢献を考慮」について
従来の相続法でも寄与分制度がありました。
寄与分とは、被相続人の生前にその財産の維持や増加に貢献した相続人がいた場合、他の相続人との間の不公平を是正するために設けられた制度です。
ただし寄与分を主張できるのは相続人に限られていました。
例えば、長男の妻が長男の父(義父)を介護している場合、長男の妻は相続人ではないため寄与分を主張できず、療養看護等の貢献を相続分に反映させる仕組みがないため、相続分配が不公平となるケースもありました。
改正相続法では、被相続人の相続人以外の親族が、無償で療養看護等をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加があった場合、相続人に対して「特別寄与料」として金銭の支払いを請求することができるようになりました。
施行は2019年7月1日です。
出席報告
☆佐々木 仁朗 出席委員長
8月20日 26名( 0名MAKEUP)(5名出席免除)26/31 83.87%
8月 6日 11名(20名MAKEUP)(6名出席免除)31/31 100.00%
7月30日 28名( 0名MAKEUP)(4名出席免除)28/33 84.85%
委員会報告
☆親睦活動委員会委員長 山中 英彦 会員
【8月の誕生日】
河南和幸 昭和24年8月7日
真野 博 昭和24年8月20日
押部浩二 昭和37年8月3日
山本裕一郎 昭和47年8月29日
☆会員拡大委員会委員長 押部 浩二 会員
8月27日、次回、会長ゲストとして、入会の可能性のある方が2名来られます。歓迎してください。
その他の報告
☆なかよし会 大谷秀明会員
第108回コンペ 寄神会員が優勝しました。
BBは野田会員です。
☆なかよし会 寄神 正文 会員
第109回コンペは、10月9日です。
また、会運営に関する書面を確認してご意見ください。
ニコニコ箱
岩野昭 さん 残暑お見舞い申し上げます
志磨憲一郎 さん 長いお休み みなさまごくろうさまでした
松本考史 さん 日に日に涼しくなってきました!
寄神正文 さん 第108回ゴルフコンペ 優勝しました
岩﨑重曉 さん 押部さん 茂木立さん 来週入会候補者の来場楽しみしています。
山中英彦 さん 納涼家族例会にご参加頂いた皆様 ありがとうございました。
吉井邦弘 さん 6日の納涼家族例会 お世話になりました。
河村公逸 さん 残暑お見舞い申し上げます
例会予定
9月10日(火)1262回
当 番 真野 博 会員
9月17日(火)休 会
9月24日(火)1263回 「米山月間に因んで」
当 番 河南 和幸 米山記念奨学会委員長
本日のRCソング・BGM
☆RCソング
「涙そうそう」
☆BGM
「涙そうそう」
「花」
「少年時代」
茂木立 仁副幹事
mogitate@kobehit.com