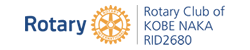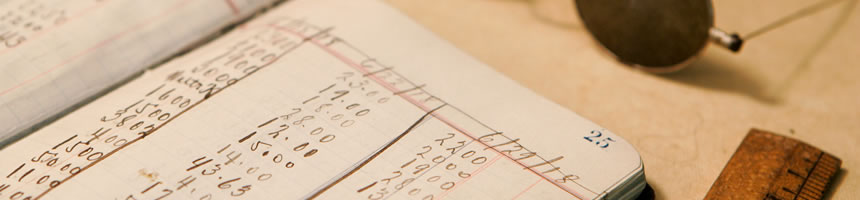
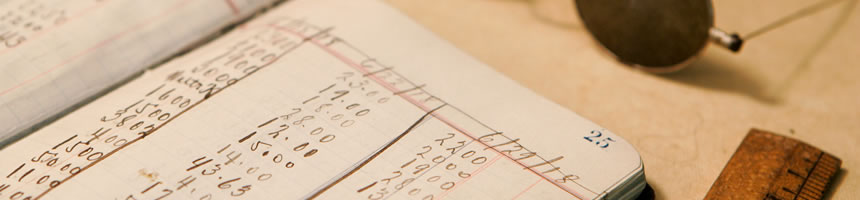
No.05 2021年8月17日号
今週の内容
☆2021年8月17日(火)第1329回
「 浦戸のルーツ 兵庫津の魅力 第1部 」
スピーチ 一般社団法人 よみがえる兵庫津連絡会
髙松 良和 氏 礒野 和久 氏
当 番 國田 正博 会員
次週予定
☆2021年8月24日(火)第1330回
「 浦戸のルーツ 兵庫津の魅力 第2部 」
スピーチ 一般社団法人 よみがえる兵庫津連絡協議会
髙松 良和 氏・礒野 和久 氏
当 番 真野 博 会員
前週の報告①
☆2021年8月3日(火)第1328回
ハイブリット例会
「 蒙古襲来 パートⅠ 」
スピーチ 税理士 笹倉 宣也 氏 (神戸西RC)
当 番 河村 公逸 会員
司 会 藤定 真由美 副SAA
点 鐘 永井 幸寿 会 長
前週の報告②
ロータリーソング
ソングリーダー 寄神 裕佑 親睦活動委員
「 君が代 ・ 我等の生業 」
BGM
「 Home On The Range 」
「 It’s A Sin To Tell A Lie 」
「 Fascination 」
ピアノ演奏 森田 純子 さん
会長報告
今日は笹倉先生に「蒙古襲来パートⅠ」の卓話をしていただきます。たっぷり時間をとっていただきますので,私の話は簡単にしましょう。
マンボウ,蔓延防止措置が発動され,月曜日から飲食店はアルコールが提供出来なくなりました。でも,もう少しの辛抱だと思います。ワクチンの普及で,今年の末か来年の初めにはコロナはおさまるのではないでしょうか。
それまでは,若山牧水の歌のように行きたいと思います。
「白玉の歯にしみ通る秋の夜の酒は静かに飲むベかりけり。」
今週の土曜日が立秋です。もう秋です。
幹事報告
1 兵庫県のまん延防止の措置によりアルコールの提供は出来ませんので月初の乾杯は中止とさせていただきます。2 まん延防止の措置によりホテルオークラの会場が20時までしか利用できませんが、本日例会後、理事会を開催しますので、理事の方々はご出席お願いします。
3 国際ロータリー日本事務局 業務推進・IT室より
2021年8月「会員増強・新クラブ結成推進月間」のリソースが送付されています。
4 ガバナー事務所より
① ロータリー奉仕デーの一環といたしまして、9月12日(日)に開催の地球環境保全プロジェクト(海岸清掃)のご案内が届いております。詳細は、幹事または事務局に確認ください。
② 8月2日~8月31日の期間、兵庫県はまん延防止等重点措置の対象地域となりますので引き続き、在宅勤務を併用しながら業務を進めていくとの案内が届いております。
1.勤務体制:事務所と在宅の併用勤務
(原則として非対面業務となります)
2.勤務時間:平日午前10時~午後5時
(時間外については、原則として翌日のご対応となります)
3.対象期間:2021年8月31日(火)まで
4.お問合せ:メールでのお問い合わせにご協力をお願いいたします。
お電話でのお問い合わせは原則ご遠慮ください。
5 国際ロータリー経理室より
国際ロータリーで行っている世界的な財務管理システムの移行にあたり、
7月以降にいただいたご寄付の手続きに通常よりお時間をいただくことが予想されるとの案内が届いております。
6 一般社団法人ロータリーの友事務所より
新型コロナウイルス感染症に関する友事務所対応の件が届いています。
1)『友』配布に関して
編集・製作工程の関係と協力し、極力第1例会日にクラブへお届けできるように製作していきます。万一遅れる場合は別途ご案内します。
2)友事務所運営について
今後も、基本的に友事務所職員は時差出勤と在宅勤務併用で業務にあたります。今後の状況を判断しつつ、期間を変更する際は改めてご報告いたします。ご了承ください。
友事務所に対する問い合わせ対応時間を10:00から17:00とします。
3)問合せ等について
編集部および管理部に対する問合せは、メールにて対応いたします。
①編集部 hensyu@rotary-no-tomo.jp
※記事の投稿等はウエブサイトの投稿フォームも併せて活用ください。
②管理部 keiri@rotary-no-tomo.jp
7 ガバナー月信、ロータリーの友が届いておりますのでお持ち帰り下さい。
8 次週、休会(定款第7条により)ですのでお間違えの無いようお願いいたします。
9 ロスターが2部ポスティングされています。お忘れのないようにお持ち帰りください。
10 今月のロータリーレートは1ドル110円です。
卓話
「 蒙古襲来 パートⅠ 」税理士 笹倉 宣也 氏 (神戸西ロータリークラブ)
当 番 河村 公逸 会員
日本の国難 PART Ⅰ 蒙古襲来 (1274年~1281年)
目的 日本征圧(第一段階として、九州征圧)
1.マルコ・ポーロから開いた黄金の国 ジパング
2.中国大陸ではあまり採れない硫黄が九州では大量に産出
3.元の敵である、南宋と日本は友好的
巨大なモンゴル帝国から見て、東の端の小さな島国は、 最後の征服地候補
従来の定説
[1274年 文永の役]
モンゴル帝国(元)が、900隻の軍船により3万人の 兵力でもって、日本へ進攻。
途中、対島、壱岐を壊滅させ、博多に上陸、一騎打ちの日本軍を集団戦法で破り、
博多の街を攻略、 太宰府の手前の水城まで進軍したが、 その夜、神風が吹いて一隻残らず撤退した。
[1281年 弘安の役]
朝鮮半島から高麗軍4万人、征服した南宋から 南宋軍10万人、計14万人で、日本へ進攻。
鎌倉幕府は事前に了見し、九州北部沿岸、 長門(山口県)まで、約100kにわたる、
高さ2mの防塁を築き、北部九州の海岸線で激戦を繰り広げ、夜には、
船どうしの海戦となり、また神風が吹き 元軍は引き上げていった。
経緯
1271年 1月
フビライは征服した高麗に軍隊と食料を集結させる
1274年
南宋との戦いにめどが立ったため、 日本侵攻の大号令を発する。
高麗に対し6ヶ月以内に大型軍船300隻、小型上陸艇300隻、水汲み艇300隻の建造を厳命。
大工、人夫、3万人以上を徴発。
―2回目以降の使節団の目的―
・上陸地点の把握 ・地形(山、川、湿地) 地図作り
・目標攻撃地点(進軍経路) ・天候
・武器等の装備品 ・食材事情(確保)
・動員兵力
第1ラウンド(文永の役) 1274年
日本 元
トップ 鎌倉幕府 モンゴル帝国
第7代執権北条時宗(18才) 第5代皇帝フビライ・ハン (59才)
兵力 九州御家人 1万6000人 蒙古、高麗兵 4万4000人
(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分) 戦闘兵 2万6000人
騎馬兵 5300騎 馬 700~1000頭
郎党歩兵 10000人 900隻
武器 大鎧 綿甲
和弓(長弓) 射程240m 短弓 射程200m
日本刀 短剣
なぎなた 槍
てつはう
北条時宗
日本に来た高麗人、南宋の商人、 多くの禅僧からあらゆる情報を収集していた。
若い指導者を中心に幕府の補佐役達は全力で支える。
国運をかけた対決が始まることを予測。
1.25歳になった将軍を更迭
2.権力を絶対とするため、外交で意見の違いもあった義兄を殺害
3.九州の守護、名越家を滅ぼし、北条一族を送り、 九州の防衛体制を強化するとともに、
直接軍事命令を下すことができるようにした。
4. 全国の寺社に異国降伏の祈願を要請 ―法戦とする― 全国規模で情報を通知し、世論を統一
5.1271年 異国警固番役を設置
鎌倉武士団の特徴
・重装長弓騎兵 ・大鎧
・和弓 ・日本刀
・薙刀(なぎなた) ・和弓による馬上からの正面直射
・重装騎兵の集団突撃(10人で3.3t)
・接近戦は日本刀による引き切り (馬上より刺してもすぐぬける)
・先駆け 打首 討死 ⇒ 恩賞
・夜討ち、焼き討ち、奇襲が原則(ルールなし)
食料 水
蒙古軍 46,000人 →食料 5,100トン 3ヶ月
水 2トン ・・・ 腐る
↓
400隻
日本軍 16,000人 →米 2,300俵 秋の収穫後
武具(矢)
馬、牛車 1ヶ月
(中国地方、九州よりかき集める)
↓
10,000人
1271年 新暦 11月3日
朝鮮半島 合浦(現在の馬山) 出航
蒙古軍 6,000人
高麗軍 20,000人
新造大型軍船 126隻 ×120名+60名=180名
中型軍船 150隻 × 90名+20名=110名
上陸用舟艇 300隻 × 16名+ 6名= 22名
補給用水汲船 300隻
計 約880隻 計 4万4000人
内 兵士 2万6000人
高麗から18日間 狭い船内 船酔い ⇒ 振動病 嘔吐、神経麻痺、食欲
11月5日
対島に襲来 約1000名の蒙古軍上陸。対島御家人 宗資国80名で応戦、全滅。
村を焼き払い、島人をほぼ殺害。女子は手の平に穴をあけ、縄を通して船壁に並べ立てる。その他の子ども、男女、約200人を奴婢として高麗へ送る。
日連記述 「兵衛次郎、対島を脱出、博多へ出航、襲来を告げる。」
11月14日
壱岐島に上陸 平景隆以下1000人の兵が応戦、全滅。
日連記述 「壱岐対島九国の兵、並びに男女、多くは殺され、 あるいはとらわれ、あるいは海に入り、 幾千と云う事なし」
大宰府に状況が伝わり、京都、鎌倉へ急報を発する。九州北部の御家人が、大宰府に集結し始める。
11月16日~17日
長崎県 北部沿岸の平戸島、松浦、鷹島、能古島に上陸 松浦党が応戦するが、数百人が死亡、壊滅。
大宰府より京都、鎌倉へ急報を発する。福岡、熊本、大分、佐賀、長崎の御家人が集結 鹿児島、宮崎からも出陣。
11月18日~19日
日本軍主力部隊が、大宰府から博多東部へ移動 約5000人。
20日 6時
蒙古軍 博多湾西側の百道原、今津浜に上陸開始。日本軍 大宰府の征圧を目指してくるものと予想し、 大宰府へ通じる、博多東側の筥崎に本陣を置く。
西側は、少人数の地元武士しかいなく、 第1陣300名の蒙古軍に少数突撃を開始。
100人単位の集団で日本軍を取り囲み、これを殲滅。
蒙古軍はそのまま東の高台の赤坂へ進軍。
1時間後、第2陣 300名上陸、赤坂方面へ。
地元の武士団が敗れたとの報により、筥崎の主力騎馬隊が西の赤坂へ100騎単位で移動。
180人乗りの300隻の大型軍船から、 全軍2万6000人の兵士と、 馬を浜に上陸させるには、 15人乗りの300隻の小型上陸艇が船団と浜の間を 1隻当り
10往復しなければならない。よって、蒙古軍は一度に上陸できないため、 大規模集団を形成できず、戦力の逐次投入という、 戦術的にやってはいけない結果となる。
また、博多の多くが湿地帯のため、 靴が革と鉄製の底のため、蒙古兵は機動性が失われて、 そもそも船酔いの体力消耗も相まって、 戦闘力が脆弱。
1往復、片道20分、乗り降り10分を見て約1時間 全員上陸するには10時間必要。
夜明けの午前6時に上陸を開始したとしても、 午後4時となり、11月中旬はもう暗くなり始める。 ―馬は、すべて上陸させることは不可能-
蒙古軍は、矢を防ぐ盾を持つ歩兵を先頭に、 その後ろに、槍歩兵、騎馬隊、後方に弓歩兵が集団となり、 全員歩行速度で前進。 矢の射程に達すると、ドラを打ち、 弓兵が45度の角度で一斉射撃。(弓は1人30本) 盾兵がしりぞき、槍、少数の騎馬兵が前進。
鎌倉武士団は、楯兵、弓兵、騎馬武者、その後ろに、 従者郎党の薙刀歩兵が展開。
歩行速度で前進、弓射程に入ると、弓兵が遠距離射撃。 敵陣から200mあたりで楯兵が開き、 蒙古軍の弓が降りそそぐ中、重装騎兵が集団となって、 弓を直射しながら突進、 その後を薙刀歩兵が替え馬と共に前進。 (弓は1人24本)
弓の練度、矢の直進性は、和弓が勝り、 威力は蒙古短弓の3倍程度、楯、綿甲は貫通。
接近戦は、短剣を持つ蒙古兵に対して、 引き切れる長い日本刀が、綿甲ごと切断。
反りのある薙刀の威力もあって蒙古兵を圧倒。
騎馬兵の、反復突進攻撃に、蒙古軍は後退を繰り返す。 遅れて上陸させた、矢、水等の補給は、どの部隊、場所に運んだらいいか分からず、撤退兵と上陸兵が入り乱れてのパニック。
東の赤坂の陣から西の鳥飼潟へ撤退。 鳥飼潟で日本軍と激戦。
日本の武士団が補給のため兵を引いた午後3時頃、 死者と軍馬を放棄して、全軍が船に引き揚げ開始 蒙古軍、戦死者約5,000人。
その夜、午前3時過ぎ頃、総数300隻で 博多湾を出て壱岐に向かう。
10時間後に壱岐に到着。休息と船の修理、傷の手当、水の補給を行う。
その夜、北西風が強くなり始め、風速15mぐらいか。 蒙古軍船が走錨始める。
湾の北西岸に吹きつけられ座礁し、 軍船約200隻、上陸船200隻が沈没。
約9,000人溺死 1ヶ月かかって高麗へ。
結果、蒙古軍未帰還者 1万3,500人
― 勝利の要因 ―
蒙古軍 日本軍
1.モチベーションの違い いやいや 恩賞・朝敵
(征服した元の命令) (先駆、分捕、討死)
2.長期の航海 ひどい船酔い ―
3.上陸作戦の失敗 一度に大量の兵士を
上陸させられない
4.補給が困難 大型船からの補給の難しさ
5.武具等の違い 軽装 重装
(軽装歩兵) (重装長弓騎兵)
短弓(練度) 和弓(長弓)
綿甲 大鎧
馬少ない 馬多い
短剣 日本刀
(反りなく、たたく、突く) 恐ろしく切れるが
折れない、曲がらない
(反りがあり、引き切る)
(短く、重い) (長く、軽い)
てつはう
陶器の容器に火薬を ―
詰め込んだもの
(投石器はなし)
元側記述
「兵隊は、弓と刀を装備して、鎧を着込んでいる。 騎兵は集団戦法で連携している」
「怖がらせる為に、武士の隊長クラスの首をかかげたら、 それを取り返すべく、さらに攻撃に熱を帯びた」
「てつはうを使っても、遠くから弓矢が飛んできて こちらの弓矢が届かない」
「捕虜を盾にしても、最初から捕虜ごと殺しにくる」
「日本軍は、指揮官が死のうが、親が死のうが、 子どもが死のうが、容赦なく戦い続ける」
結果 ―事実― (文永の役)
新暦11月に神風というものは吹かず、鎌倉武士団が、 被害を出しながらも、蒙古軍を博多で撃退。
補給がままならない蒙古軍は船へ。
撤退途中で、11月の強い北西の季節風による 荒波で一部が沈没。
「冬十月、元軍は日本に入り、これを破った。しかし元軍は整わず、また矢が尽きたため、ただ四境を慮掠して帰還した。」
元史
「たとえ風に遭わず、彼の国の岸に至っても、 倭国は地広く、徒衆が多い。彼の兵は四集し、我が軍には後援はない。
救兵を発しようと思っても、 ただちに海を飛んで渡ることはできない。」
第2ラウンド (弘安の役 1281年)
・元、高麗軍 40,000人
900隻 VS 鎌倉幕府軍
・南宋軍 100,000人
3500隻
計 約140,000人
出席報告
☆細谷 眞弓 出席担当委員
8月 3日の出席者 28名
7月27日の出席者 27名
7月20日の出席者 23名
委員会報告
☆松本 考史 親睦活動委員長
本日のゲストは、神戸西ロータリークラブの笹倉宣也さん、米山留学生の劉永恩さんです。
今月のお誕生日を迎えられる会員は、河南和幸会員(8月7日)、真野博会員(8月20日)、山本裕一郎会員(8月29日)です。
代表して河南和幸会員に記念品を贈呈します。
劉さんに奨学金を贈呈します。
その他の報告
☆なかよし会幹事 細谷 眞弓 会員
7月29日に開催されたなかよし会ゴルフコンペの結果をお知らせします。
優勝は志磨健一郎会員、2位は岡田利夫会員、3位は寄神裕佑会員、ブービーは細谷会員でした。
次回は10月7日に開催予定です。皆様ご予定ください。
ニコニコ箱
☆橋本 猛央 副SAA代理
吉井邦弘 さん 今月のロータリーの友に
「帰宅して マスク外して 深呼吸」という句が載りました。
河南和幸 さん バースデープレゼントありがとうございます。
8月7日で72才になります。
河村公逸 さん 笹倉さん 本日は卓話宜しくお願いします。
岡田利夫 さん 第114回仲良し会2位になりました。
回ったメンバーも良かったのですが、
一緒に車に乗ったメンバーで1位2位3位となりました。
内波憲一 さん 笹倉さん ようこそ今日はよろしく
寄神裕佑 さん 先日のコンペお疲れ様でした。
今年のレコードでも 優勝届かずです。
橋本猛央 さん 本日 副SAA代理です。ありがとうございました。
例会予定
8月24日(火)第1330回 「 浦戸のルーツ 兵庫津の魅力第2部 」
スピーチ 一般社団法人 よみがえる兵庫津連絡協議会
髙松 良和 氏・礒野 和久 氏
当 番 真野 博 会員
8月31日(火)第1331回 「 会員卓話 」
当 番 紀伊國谷 隆 会員
9月 7日(火)第1332回 「 東京オリンピックに参加して 」
当 番 平山 一哉 会員
9月14日(火)第1333回 「 会員卓話 」
当 番 茂木立 仁 会員
本日のRCソング・BGM
ロータリーソング
「 われは海の子 」
BGM
「 A Whole New World 」
「 My One And Only Love 」
「 Silver Balloon 」
山﨑弘子 副幹事