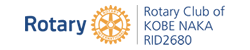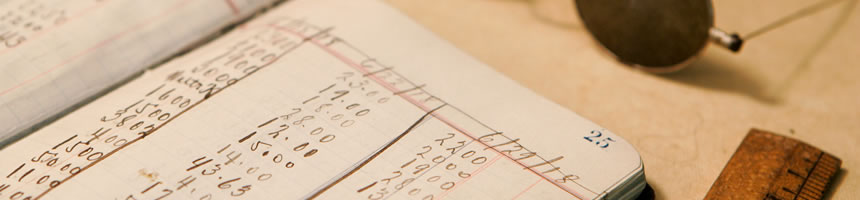
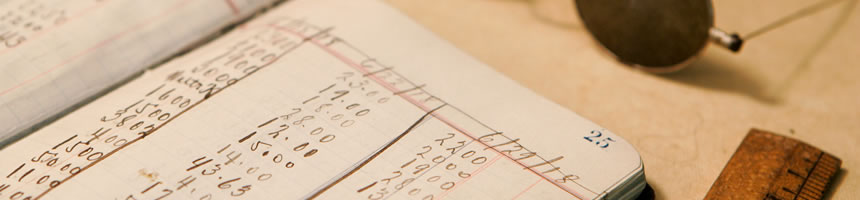
No.27 2022年2月15日号
今週の内容
☆2022年 2月15日(火)第1352回 ハイブリッド例会
「ロータリーの変化にどう対応するか」
スピーチ RID268パストガバナー 矢野 宗司 氏(加古川中央RC)
当 番 宇尾 好博 会員
次週予定
☆2022年 2月22日(火)第1353回 ハイブリッド例会
「 断捨離 」
当 番 山中 弘光 会員
前週の報告①
☆2022年 2月 1日(火)第1350回 ハイブリッド例会
「 蒙古襲来パート2 」
スピーチ 税理士 笹倉 宣也 氏(神戸西RC)
当 番 内波 憲一 会員
司 会 髙井 敏郎 SAA
点 鐘 永井 幸寿 会 長
前週の報告②
☆お客様紹介 松本 考史 親睦活動委員長
お客様 ゲストスピーカー
税理士 笹倉 宣也 様(神戸西RC)
米山奨学生 劉 永恩(ユーヨンウン)さん
☆ロータリーソング
ソングリーダー 岩﨑 重暁 親睦活動委員
「 君が代 」「 四つのテスト 」
会長報告
弾道ミサイル
先月,1ヶ月で,ミサイルが7回飛んできたそうです。
「もし,あのミサイルが日本に向かって飛んできたときは打ち落として良いのですか」という質問を受けることがあります。これ打ち落とせるのかどうか,不安ですね。
答えは,「打ち落とせます。」です。
弾道ミサイル等が日本に向かって飛んできたとき,一定の要件があれば,打ち落として良いという手続きを定めた法律があります。何という法律か知ってる人はいますか?
日本国民としては知っておく必要があるかと思います。
自衛隊法82条の3です。
防衛大臣は,弾道ミサイル等が,我が国に飛来する恐れがあり,落下による我が国の領域における人命又は財産に対する被害を予防する必要があるときは,内閣総理大臣の承認を得て,自衛隊の部隊に対して,我が国の領域又は公海の上空で破壊する命令を出すことが出来るとあります。
「領土」があり,その周りに12海里の「領海」があり,領土と領海の上の空間が「領空」です。この領土と領海と領空を「領域」と言います。領域とは,国家の主権の及ぶところです。我が国の「領域」の人命や財産の被害を予防するため,我が国領域又は公海の上空で,「公海」とは,領海や排他的経済水域ではないところです。弾道ミサイル等の破壊を命じることが出来ます。
北朝鮮の弾道ミサイル,中距離弾道ミサイルなのでテポドンではなくてノドンだと思いますが,10分で日本に来ます。すると,防衛大臣が「総理,ノドンが我が国の領域に飛んできます。打ち落として良いですか。」と電話したら「総理は今お手洗いです。」と言ったときはどうなるんでしょう。
「お手洗いが長引いています」となったら,更にどうなるんでしょう。
そこで,事態が急変して,同意を得るひまがない緊急のときは,総理大臣の承認を得た「緊急対処要領」で予め部隊に命令を発することが出来るとされています。
日本に向かってミサイルが飛んできたときは,法律上打ち落とせるんだと言うことは知っておいてください。
幹事報告
1 神戸第2グループIMは新型コロナウィルスの感染拡大のため4月23日(土)に延期になりましたが、次週の休会の変更はありませんのでご注意ください。2 地区大会の3月5日(土)、3月6日(日)の開催ですが、新型コロナウィルスの感染拡大のため、大会特別委員会を除く各プログラムのすべてをオンラインに変更し、飲食を伴う行事もすべて中止とする案内が届いております。
開催日: 2022年3月5日(土)~6日(日)
開催方式:
3月5日(土)
13:00~ 各大会特別委員会 対面式会場開催
14:00~ 会長・幹事会 オンライン(Zoom使用予定)
14:30~ ロータリーファミリーの集い オンライン(Zoom使用予定)
15:00~ ロータリー研修セミナー オンライン(Zoom使用予定)
講演15:45~(講師:田中久夫氏)
*セミナーにオンライン参加する際、お名前とメールアドレスの入力が
必要な場合があります。
各行事の参加・視聴用URLは、追ってお知らせいたします。
17:30~ ロータリーディナーパーティー 中止
3月6日(日)
13:00~ 本会議
午後からの開催に変更いたします。(終了時刻17:00を予定)
YouTubeによるリアルタイム配信:2680地区ホームページにて公開いたします。
14:00~ 本会議記念講演(講師:山極壽一氏)
17:00~ 会員家族懇親会 中止
登録方法:3月5日(土)1日目
地区大会1日目の会長・幹事会、ロータリー研修セミナー、ロータリーファミリーの集いのご登録は、地区Web管理システムから引き続きお願いいたします。
なお、緊急時に備え、この3行事にご出席の方につきましては、参考備考に、当日つながる携帯番号のご入力を必ずお願いいたします。
会長・幹事会では、会長の採決を必要とする議案についての説明がありますので、ご出席の程よろしくお願いいたします。
3月6日(日)2日目
地区内会員様全員登録となりましたので、本会議の登録は不要です。
登録締切:2月17日(木)
3 兵庫県のまん延防止の措置により、月初の乾杯は中止とさせていただきます。また、ハイブリッド例会は継続しますが、不安を感じる方はZOOMにて参加をお願いします。
4 前々回の幹事報告でもお伝えしましたが、現事務所は、2月9日(水)にグリーンシャポービルに移転いたします。
2月中は移転作業に伴い事務局が不在の場合もありますので、ご用の方は事前確認をお願いいたします。
5 本日例会後、銀杏の間にて理事会を開催しますので、理事の方々はご出席お願いします。
6 本日、ガバナー月信、抜筆のつづり、ローターリーの友をポスティングしていますので、お忘れなくお持ち帰り下さい。
7 ピアノの森田純子先生は、体調不良のため本日もお休みです。
8 今月のロータリーレートは1ドル115円です。
卓話
「 日本の国難 Part Ⅱ第2ラウンド 蒙古襲来 弘安の役 1281年 」
スピーチ 税理士 笹倉 宣也 氏(神戸西RC)
前回のおさらい
文永の役 1274年
結果(事実)
新暦11月に神風というものは吹かず、鎌倉武士団が、被害を出しながらも、蒙古軍を博多で撃退。補給がままならない蒙古軍は船へ。撤退途中で、11月の強い北西の季節風による荒波で一部が沈没。
次の課題
鎌倉幕府第7代執権 北条時宗(25才)、 文永の役を検討し、次の施策を実施
1.造船数を向上させて、水夫、舵取りを養成、増員、品質の高い(波に強く、スピードの速い) 船の建造(造船技術の向上)
2.上陸させない
A.元寇防塁の建造(建治2年3月より)
・九州北部~山口県(約100㎞)
・海側は高さ2m、後ろ側はなだらかにして登れるように
B.海岸に乱杭、砂浜に木柵設置
C.弓矢等の武具の大量生産
D.船の建造と徴収→2900隻
E.宿舎の建設
一段目の備え
博多湾中心に防塁を築き、数千人の兵士が寝泊まりできる建物を建設。九州全土、四国、関東から兵を動員、 海には乱杭、海岸に木柵、多くの船を海上に配置
二段目の備え
弟の北条宗頼を長門探題に任命。長門地方の防衛のため、中国地方の御家人を海岸付近に配置
三段目の備え
蒙古軍が大宰府政略を変更し、直接、都に近い山陰海岸に来襲してくることを想定し、中国山陰方面の防衛に弟の宗頼を任命、山陰地方の守護、御家人をあてる
四段目の備え
蒙古軍の一部の兵が長門(関門海峡)の防衛ラインを破って、瀬戸内 海に侵攻してきたことに備え、播磨方面でくい止めるため、この地方の御家人を瀬戸内海に配置
―蒙古軍動員兵力―
東路軍 (朝鮮半島より)
総兵力 40,000~42,000人
1.高麗軍 10,000人
2.蒙古漢軍 15,000人
3.水夫、補給 16,000人
900隻
・食料 11万石(4ヵ月分) 戦艦 300隻
19,800トン バートル 300隻
水汲船 300隻
・回回砲を載積
江南軍 (中国上海付近より)
総兵力 100,000人
1.南宋軍 60,000人
2.水夫、補給、農民 40,000人
3,500隻
(内20,000人は植民、移住のための農民)
・食料 40万~50万石 大型戦艦 1,200隻
81,000トン バートル 1,200隻
水汲船 1,100隻
―鎌倉幕府動員兵力―
九州全土、四国、中国地方 約10万人
近畿(六波羅軍) 約6万人
(内 戦闘兵力 約8万人)
女子、及び15才以上の男子を徴兵
6月3日
元の東路軍(軍船900隻 40,000人) 高麗合浦を出発
6月21日
対島上陸
7月4~5日
東路軍別動隊 長門上陸を試みる
7月6日
東路軍、博多湾侵入。湾内にて日本軍が迎撃。
7月6日夜
「肥前の御家人、草野次郎経永が、敵の上陸を待たず二艘の船に家臣を分乗させ、暗闇の中を櫓音を殺して、敵船の一艘に忍び寄り、乗り移ることに成功した。
不意を突かれた船内では元軍が慌てふためき、逃げ回るのを追って斬りかかり、突き殺し、あっという間に21人の首を取り、船に火をかけて引き揚げてきた。」
「元軍は、日本船が近づくのを防ぐため、船と船とを鎖で連結し、近寄る小舟を石、弓で沈めた。」
大陸育ちの兵士の、上陸作戦はほぼ初めて。上下左右に揺れ動く船内で、船縁を片手でつかみ、片手で武器を持ち上陸を待つ。陸地の日本軍からの猛烈な数の矢が飛んできて、16人乗りの上陸艇の狭い船上は、身動きが取れなくて、立ち上がることもできないため、船上から矢を精度高く射ることはほぼ不可能。
日本軍は、バートルに陸上から矢を射たり、熊手で船を引っ掛け、長い薙刀で斬りつけていく。日本の軍船の攻撃に耐えて、海岸まで前進すると乱杭にたどり着く。ここで前進を阻まれ、乱杭そばの小型の別の日本船から、弓と薙刀の攻撃を受ける。これを突破し、海岸線に近づいても、浜辺からの猛烈な弓の攻撃がある。浜辺に上陸し、すぐに楯兵を並べたとしても、浜辺に設置された木柵と楯兵に守られた重装弓騎兵が待っている。重装弓騎兵からの和弓の直射は、蒙古の綿甲、楯を貫通する。その後方に高さ2mの石垣の防塁があり、約4㎞幅に約1万人の弓、薙刀兵が防塁の上で待っている。また、防塁の前の浜辺の重装騎兵は死ぬまで戦う。例え上陸できたとしても、バラバラでの上陸のため、集団による隊列、あるいは兵種別の隊列は組めない。かつ、矢の補給もままならない。
日本軍は上陸してくる小型艇を順番に攻撃していく。よって、小型の上陸船艇に乗り換えるしかない。上陸動作は不可能。
―上陸はできなかった―
東路軍は6月29日~7月5日の6~7日間、博多湾にて何度も上陸を敢行したが、日本軍の反撃によりすべて失敗する。その時、船上から回回砲を使用。
鎮西要略
「異賊舸船上の高楼に登り、火箭鉄砲を放ち、大いに禦をなす。我兵、之が為に死創を被る者若干」
7月7日
上陸できない東路軍は沖の志賀島へ移動。日本の軍船は次々と志賀島に向けて漕ぎ出し、海上と島に上陸して攻撃をしかけた。
―日本軍2,000隻以上の船で博多湾より志賀島へ追撃―
7月8日
志賀島にて、東路軍と日本軍40,000人が激戦。
「去る6日より13日に至るまで、昼夜の間合戦し、撃ち殺す、蒙古兵は1,000余人。日本軍は蒙古の大型艦からの投石、弓による攻撃により大きな損害を受ける。」
―回回砲―
最大射程距離約200m以内。戦艦からの発射は陸上に到達しない。
日本の和船(小型船)約1,800隻と、バートルの戦い。
和船は小さいので、乗船人数の多い大型戦艦に移乗攻撃をせず、小型の乗船人数の少ないバートルを攻撃し、水夫を襲い、バートルを捕獲する。
志賀島の蒙古軍に対し、出陣した大友軍、薩摩軍は野営をしながら毎晩夜襲を行う。2~3日後、弓矢が不足し、熊手、薙刀、薙鎌を使い夜襲による船への攻撃を続ける。
蒙古軍 昼夜を問わない日本軍の攻撃に苦戦する。
「去る6日より13日に至るまで、昼夜の間合戦し、撃ち殺す蒙古兵は1,000余人、残るところの船共引き退く由を申しけり」
蒙古軍の大陸での戦い
馬の多さと優れた騎射能力、後方からの弓矢の補給、怒砲、投石器、土木工事などのよる城郭攻略・・総合力の差で勝っていた。投石器は小型上陸船には、兵と共に乗せられない・
高麗側記録
「7月8日、日本軍と力戦して、斬首300余級を得たが、洪茶丘は、日本軍の突撃を受け、馬に乗って敗走し、一時は危険な状態であった。翌9日にはさらに、敗戦を重ねたうえ、軍中に疫病が発生し、死者は3,000人におよんだ」
7月5日~12日
熊手で船を引っ掛け、まず弓を射ち、刀と薙刀を振りかざして移乗する。結果6~7日間で、東路軍の死者約5,000人、病没者3,000人以上、感染による戦闘不能者6,000人。日本軍が圧倒する。
引き続き、日本軍は博多湾内において、船にて、夜襲を繰り返す。
夏の暑さにより、船内は蒸し風呂状態、食料・水は腐る、船酔いによる衰弱、長期の睡眠不足、1ヶ月以上体を洗っていない、伝染病の発生、極度のストレス
7月13日
戦闘維持できないため、志賀島から壱岐島へ撤退、江南軍との合流を目指す。 1.壱岐島を占領して、日本侵攻のための橋頭堡とする
2.兵士の治療
3.戦艦の修理
4.食料、水の確保
7月18日
江南軍(軍船3,500隻 100,000人)予定より遅れて、中国 寧波を出発。日本軍、博多湾から北西55㎞の壱岐島へ追撃。
7月25日
江南軍先遣隊が壱岐に到着。東路軍に合流地の平戸島付近への移動を伝える。
7月29日
日本軍、壱岐島へ追撃、壱岐にて激戦
8月2日
日本軍の奮戦と疫病蔓延により、壱岐から撤退
壱岐沖を漂った後、西の平戸島へ移動
8月5日~6日頃
平戸島にて合流
8月27日
元軍(東路軍+江南軍)、 東の松浦沖の鷹島へ移動
鷹島沖に停泊した元軍艦隊に、日本軍2,400隻が総攻撃
(鷹島沖海戦)
「元軍の大船団が鷹島に集結中との情報を得、再び博多湾に集結中の軍船に乗り込んで、鷹島近海に進出し、8月27日夜、敵の不備に乗じて夜襲を敢行した。引き続き、翌28日まで猛攻を加え、敵に大損害を与えた。」
日中の明るい時は、日本の軍船に対して弓矢、弩、石弾で攻撃する。しかし、日本軍の得意の、夜襲攻撃は、防ぎようがない。1隻の蒙古の大型軍船に対して、日本船は20隻以上で対応する。石弾は、40個~50個を一度で使用するので、すぐ在庫がなくなる。また、日本軍は兵士の少ない300隻の大型兵站船を中心に、火矢、移乗により、昼夜の別なく執拗に攻撃。また、1隻のバートルに4隻以上の小型船が取り囲み、壊滅する。上陸用船艇が無くなると、戦艦は単なる大型船となり、湾内を漂うだけとなる。
8月30日深夜
大暴風雨 ―台風襲来―
日本船からの攻撃を防ぐため(兵士の移動が可能であり、側面を防ごうとするため)、戦艦どうしを鎖で結合していたことにより、台風の影響をまともに受け、ほとんどの戦艦が破壊沈没する。
上陸できないまま博多湾、平戸、鷹島近海で日本軍の
連日の昼夜を問わない攻撃にさらされ、1ヶ月近く漂い、
その後台風に遭遇した。
9月1日
台風一過の晴天の中、伊万里湾には、おびただしい数の戦艦と水汲み船の残骸で埋め尽くされる。また海上には多くの死体が浮いていた。 江南軍の軍艦は多くが、船どうしを連携していたため沈没。 残った船が蒙古兵の救助と破壊された船の修理を始める。
元軍
「残った頑丈な船で、兵卒約10万人を鷹島に残し撤退。平戸島では、軍馬70頭を降ろし、4,000人を軍船に収容して帰還。生き残った蒙古兵は、補給基地のある鷹島へ上陸。(10万人)島では日本軍の来襲に備えて、建物の補強、船の修理、ケガ人の手当、食料・水の確保。山から木を切り倒し、帰還用の船の建造を始める。4日間不眠不休で作業。
9月5日
少弐景資を総大将として、伊万里湾、鷹島へ。掃蕩戦を開始。体力、補給、武具で勝る武士団相手に戦闘意欲のない蒙古兵は降伏。
降伏者2万~3万人、その他は全滅
元史
「10万人が帰還せず、高麗の死者は7,000余人」「10万人の衆、還ることの得る者、3人のみ」「30日に大風雨がおこり、雹の大きさは拳の如し。 船は大浪のため掀播し、沈壊してしまう。蒙古軍は半ば海に没し、船はわずか400余隻のみ残る。10万人は白骨山(鷹島)に置き去りにされ、海を渡って帰る船がなく、倭人のためにことごとく殺される。」
9月15日
元、高麗軍、合浦に帰還
未帰還者 107,000余人
結果
帰還者
東路軍 4万人 → 3,000人
江南軍 10万人 → 2万~2.6万人
出席報告
☆細谷 眞弓 出席担当委員
2月 1日の出席者 24名(ZOOM出席1名を含む)
1月25日の出席者 25名(メークアップ1名を含む)
1月18日の出席者 25名(ZOOM出席 名・メークアップ1名を含む)
委員会報告
☆松本 考史 親睦活動委員
今月お誕生日を迎えられる会員
大田 宥 会員(2月11日)
山中 弘光 会員(2月20日)
細谷 眞弓 会員(2月20日)
平山 一哉 会員(2月 3日)
髙井 敏郎 会員(2月 5日)
松本 考史 会員(2月22日)
今月ご結婚記念日を迎えられる会員
吉井 邦弘 会員(2月 4日)
岡田 利夫 会員(2月 7日)
松本 考史 会員(2月22日)
代表して細谷会員に記念品を贈呈します。
ニコニコ箱
☆藤定 真由美 副SAA
永井幸寿 さん 雨ニモマケズ 尾身さんニモマケズ もう少しの辛抱です。
平山一哉 さん 笹倉先輩 ようこそ中ロータリーへ 今日も楽しいお話楽しみにして
います。
松本考史 さん 誕生日プレゼントありがとうございました。笹倉先生 本日はよろしく
お願いいたします。
例会予定
☆2022年 2月22日(火)第1353回 「 断捨離 」
当 番 山中 弘光 会員
☆2022年 3月 1日(火)第1354回 「 ハラスメント 」
当 番 山﨑 弘子 会員
☆2022年 3月 8日(火)第1354回 「 会員卓話 」
当 番 会員
☆2022年 3月15日(火)第1355回 「 会員卓話 」
当 番 会員
本日のRCソング・BGM
☆ピアノ演奏 森田 純子 先生
ロータリーソング
「 明日があるさ 」
BGM
「 A Whole New World 」 「 Fry Me To The Moon 」
「 My One And Only Love 」
山﨑弘子 副幹事 yamazaki-law@eagle.ocn.ne.jp