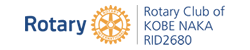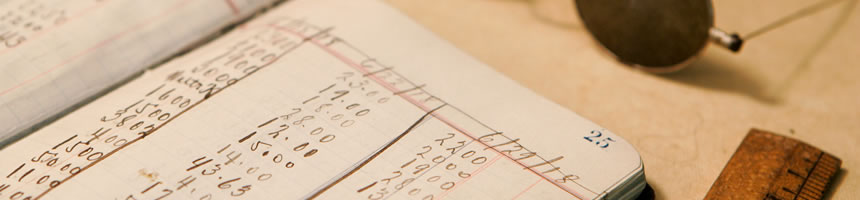
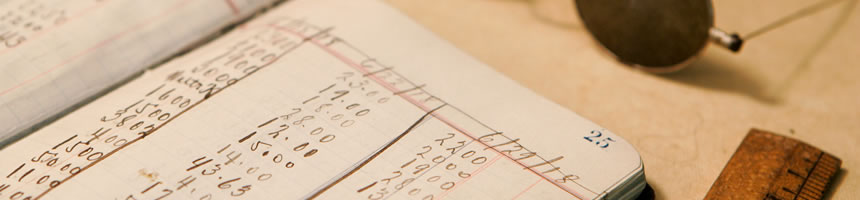
No.39 2022年5月20日号
今週の内容
☆2022年 5月24日(火)第1364階 ハイブリッド例会
「 いまさら聞けない歯医者の話 」
当 番 橋本 猛央 会員
次週予定
☆2022年 5月31日(火)第1365回 ハイブリット例会
「 6月親睦活動月間に因んで 」
当 番 親睦活動奉仕委員長 松本 考史 会員
前週の報告①
☆2022年 5月17日(火)第1363回 神戸西RC合同 ハイブリッド例会
「 留学生スピーチ 」
当 番 奥田 祐司 会員
ボルゲット・ソフィア・セリーナさん 「 緑と運の狭間 」
キン・ピョ・ウェさん 「 ほめられる恐怖 」
フース 海都さん 「 僕の日独人生 」
司 会 髙井 敏郎 SAA
点 鐘 永井 幸寿 会 長
☆松本 考史 親睦活動委員長
本日のゲスト
ボルゲット・ソフィア・セリーナさん(アルゼンチン)コミュカ学院
キン・ピョ・ウェさん(ミャンマー) 神戸YMCA学院専門学校
フース 海都さん(ドイツ)コミュカ学院
前週の報告②
☆ロータリーソング
ソングリーダー 内波 憲一 親睦活動委員
「 茶摘み 」
☆BGM
「 好きにならずに いられない 」「 嘘は罪 」「 魅惑のワルツ 」
ピアノ演奏 森田 純子 先生
会長報告
カキツバタ
5月に入り拙宅の猫の額のような庭に,アヤメが咲いてくれました。毎年群生というか沢山咲いてくれます。
このアヤメに似た花で,カキツバタがありますね。アヤメとカキツバタのちがいは,アヤメが地面に生えるのに対して,カキツバタが川などの水辺に生えることです。また,アヤメは,花びらの付け根が黄色で網のような模様がありますが,カキツバタにはこれがありません。川辺に生えるカキツバタの群生もきれいです。
伊勢物語という平安時代の物語がありますね。学校で習いましたが,「むかし男ありけり」で始まる物語です。これに「八つ橋」とい場面があります。八つ橋とは,蜘蛛の8本の足のように水路があり八つの橋が架かっているところで,今の愛知県にありました。ここにカキツバタが群生しており,旅の主人公の男性が友人と来るわけです。
友人が男性にカキツバタの5文字で歌を詠んでくださいと言ったので,男性は「唐衣,着つつ慣れにし 妻あれば,はるばる来ぬる,旅をしぞ思う。」と読みます。
「唐衣」は中国風の着物です,「着つつ慣れにし妻あれば」は着慣れたように慣れ親しんだ妻がいます。「はるばる来ぬる,旅をしぞ思う」,妻をおいて遠くまで旅に来てしまいやるせないですという意味です。カキツバタの群生を見て,男性が,何かの理由で妻を残して都から旅に出て,旅先で妻を恋しがるわけですね。妻はどう思っているかわかりませんが。夫が居なくてせいせいしているかもしれません。
この伊勢物語の「八つ橋」の題で,尾形光琳がカキツバタの群生の絵を描いています。面白いのは,光琳は,男性の妻を思う気持ちも八つ橋にも全く興味がないことです。男性も八つ橋も画いていません。カキツバタだけを画いているのです。
このカキツバタの絵は,写実的な絵と言うより,シャープなデザインという感じで,ぴ,ぴ,ぴっと描かれています。光琳はこのリズミカルなデザインに興味があったのですね。この絵に型紙を使って同じデザインのカキツバタを繰り返し画いています。
同じ芸術家でも,カキツバタの群生に対する感じ方が全く違って面白いです。尾形光琳の「八つ橋」の絵は世界的にも有名なので,季節柄インターネットでご覧になったらいかがかでしょう。「燕子花図」で出てきます。
唐衣きつゝ馴にしつましあれば
はるばる来ぬる旅をしぞ思ふ
神戸西ロータリークラブ 斎藤満知子会長ご挨拶
皆さま こんばんは。
神戸中ロータリークラブのみなさまには創立30周年記念例会そしてIMと大変お世話になり、有難うございました。
久しぶりの合同例会ですので、会員相互の親睦を深めて頂ければと思います 。また本日の卓話とても楽しみにしております。
どうぞよろしくお願いいたします。
幹事報告
1 ガバナー事務所よりヒューストン国際大会につきまして、登録締切日を5月27日(金)まで延期するとのご案内が届いています。詳細は、幹事または事務局に確認ください。
2 東京大崎RC37周年記念例会に、永井会長、奥田副会長、岩﨑会員、山本幹事で出席いたしました。
3 クラブ活動年次報告、新年度活動方針の原稿を6月7日(火)までにお願いします。
4 本日は合同例会です。斎藤会長、上根幹事を始め神戸西RCの皆様よろしくお願いいたします。
5 本日例会後、梅の間にて理事会を開催しますので、理事の方々はご出席お願いします。
卓話
運と縁の狭間ボルゲット・ソフィア
コミュニカ学院のボルゲットソフィアと申します。この例会にお招き頂き、誠にありがとうございます。本日は「運と縁の狭間」と題してお話したいと思います。
皆さん、運と縁の違いは何だと思いますか。辞書で調べたら、こう書かれていました。
運(うん)とは、幸、不幸などをもたらし、状況を動かしていく、人の力ではどうすることもできない作用。
それに対して、縁の定義は、元は仏教用語ですが、
人と人とのめぐり合わせや結びつき。関係を持つきっかけ、または繋がり
とありました。
私の答えは後ほどご説明するとして、まずは私が何百回も聞かれてきた典型的な質問についてお答えしようと思います。
私は日本の裏側の国、アルゼンチンの出身です。私の国の食べ物と言えば、パンと牛肉で、実際アルゼンチンでは人間より牛の数が多いのでどんなに食べすぎても牛肉が売り切れるということはありません。名物はやはりサッカーですが、実は私の故郷はあのメッシと同じ街です。日本と全く違う国だと思っていただけたでしょう。
またこれもよく聞かれるのですが、アルゼンチンの家族や知り合いに日本人はおりません。日本のことを知ったきっかけは、八歳の時姉の友達が日本のアニメを紹介してくれたからです。
まさに運命でした。幼い私はこの日本という不思議な国に一目ぼれしました。中学校に上がると日本語を勉強し始め、高校を卒業して大学に入学するまでの間は日本に行くために働いて貯金しました。
大学が始まってすぐ、私は母に言いました。
「大学の夏休みは日本に行くからね!」
もちろん母は心配で私を説き伏せようとしました。
「一人で行くのは望ましくないし、大学を卒業してから行ったほうが安心でしょ?」
でも私は「ずっとアルゼンチンにしか住んだことがないし、やっと行けるようになったのだから今しかない」と言い続けたら、母も私の気持ちを理解してくれました。
そして働いて貯金したお金でついに往復のチケットを買いました。行きは2020の2月で帰りは4月、二ヶ月間の滞在の予定でした。しかし、皆さんがご存知の通り、私はまだこの日本にいます。私の旅は二ヶ月では終わらなかったのです。
日本に到着してから私は島根県のNPOでボランティア活動をしていました。小さな町で保育園や小学校の手伝いをし、土日には里山の管理のため山仕事も行いながら現地の人と生活するというプログラムです。
しかし、2月から広がったコロナウィルスによって帰るはずだった4月になると帰りの飛行機がキャンセルになりました。こうしてどうにか日本には入国することができましたが、4月の段階で既にアルゼンチンには帰れなくなっていました。本当に困りましたが、NPOの人にお願いすると、ボランティアを続けることで住宅や食べ物も提供していただけると決まり、アルゼンチンの大学の授業は先生のご理解によってオンラインで受けることになりました。
島根の生活においても、伝統的な神楽の公演に参加できたり、近所で今も生きる茶道を体験できました。まさに、一人一人のつながりによって私の日本での生活が豊かになったのです。歴史的なパンデミックの裏で多くの人の優しさに触れることができ、みんなの応援によって困難な状況の中、前進できたのだと実感しました。
今思えば、その時得たものは縁だったと思います。日本に長くいられたのは運だったかもしれませんが、日本語を勉強して地元の人とコミュニケーションができたからこそ、出会った人と心を通わせることができ、夢をかなえることができました。これはまさに縁であり、私が学んだ運と縁の違いはこの点にあります。
この経験を経て今の私の夢は日本で働くことです。そのために今年から世界の人々が行き交うこの神戸の日本語学校に入り、更に自分の日本語に磨きをかけています。本当に3年前の私には想像もつかなかったことです。コロナウイルスのこと、大学がオンラインになることは自分で決めたことではありません。でも縁が結びつけた繋がりと自らの行動によって運命を変えたと信じています。
私はもともとアルゼンチンの大学では観光の勉強をしていました。そして旅とは縁を産む特別な時間だということを私は知っています。だから、コロナ後に来訪する外国人に日本の良さを伝える仕事ができれば良いと考えています。日本の文化に触れて、人と繋がることで人生も大きく変わるはずです。
ロータリークラブの皆様も奉仕と友情で、日々、世界の人々の人生を変える大切な活動をされていると思います。これからも皆様の活動によって多くの良い変化が世界にあることを私も祈っております。
以上をもって私の発表とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
ほめられる恐怖
キン ピョ ウエ
皆さん、誰かから「きれいですね」とか、「よくできたね!さすがですね」とか、ほめられたことがきっとあるでしょう。人間というのは、ほめられたら嬉しいものです。褒められたら自分自身に自信を持つようになって、やる気が高まるでしょう。でも、私はほめられても100%嬉しいわけではありません。ほめられたら、嬉しくてやる気になる一方で、辛い気持ちも感じていました。
私の母は生活用品やお菓子などを売るミニストアを経営しています。小学二年生の春休みの時、数学の勉強に役に立つからと言われて、レジカウンターで母を手伝わされました。その持、店に来るお客様たらが私をかわいがってくれて、「そんな歳でお母さんを手伝うなんて、
えらいね」とか、「さすが長女ですね」とか、よくほめられました。私がほめられることに
憧れるようになったのは、その時から始まったのかもしれません。その時から、毎年春休みになると、遊ばないで母を手伝うようになりました。
ところで、私の国では長男長女は家族の大黒柱であると言われています。ミャンマーには「一番前の牛がまっすぐ行ってこそ、後の牛がまっすぐついてくる」ということわざがあります。長女の私はこのことわざを子供のころからよく聞かされてきました。
叱られる時も、長女だからそんなことやってはいけないとか、長女だからそうしなさいとか、長女の私に対してのしつけが最も厳しかったです。というのも、「子供は親の鏡」というように、上の人を真似する可能性があるからです。
ほめられたるのが好きな私は親からの厳しいしつけに反抗しないで、素直に何でも受け入れるようにしました。ほかの子供達が遊んでいるのを見て、本当は遊びたいけど我慢して学業に励みました。
また、お正月のような親戚みんなが揃って料理を食べたり、飲んだんりする家族の集まりで、いろいろな準備とか、食べた後の片付けとかも手伝わされました。母に「どうして私だけに手伝わせるの」と、尋ねると、「長女だから頼るのよ。自分で実際にやったら妹にも教えられるでしょ」と答えました。大変なことに、大人たちに失礼になってはいけないと言われて、あいさつをすることはおろか、聞きたくない大人たちの説教も聞かざるを得なかったのです。それでも当時は親戚からも近所の大人たちからもよくほめられて、嬉しかったです。
しかし、一方で「長女だといっても子供だよ、私も勉強しないで遊びたいよ。と心の中でつぶやいていました。友達の思い出として、今でも覚えているのは、高校生の時、友達にラーメンを作ってあげた時のことです。「キンちゃんが作ってくれたラーメンが一番おいしいよ」とほめられてからは、毎回わたしが作ることになりました。わたしはおだてられるとすぐ、その気になるので疲れます。
このように、身体というより、心が疲れました。知らない間にストレスが溜まって、自分の気持ちもわからなくなりました。「彼らは本心からほめてくれているのか」と、周りの人を
疑ってマイナス思考に考えるようになりました。ほめられるためにやりたくないことを無料やりにする自分が嫌いになってきました。自分自身を高めることが、かえって自分自身を失うことになってきました。
その結果、わたしは他人の意見に流されやすくなったと思います。でも、わたしはこれから自分の弱いところを見直していきたいと思います。
ほめられるにしろ、叱られるにしろ、一番大切なのは、他人に影響されないで断る勇気をもつこと、そして、自分の心がやりたいことをやって生きていくことです。わたしは自分の気持ちが一番大切だと思います。
僕の日独人生
フース海都
皆さん初めまして、フース海都です。僕の母は日本人です。僕の父はドイツ人です。ドイツと日本のハーフなので両方の文化や人間の考え方、メンタリティを意識して育ちました。今から日独の文化を比較したいと思います。相違点は3つあります。
一つ目は話し方、表現のしかたです。日本人の話し方には一つ特徴があります。困っている時、嫌な時は直接言わないことです。元々日本では言ったことに裏の意味が多くあり空気を読むのが大事です。ドイツ語では直接嫌なことを厳しく言うことが多くあります。だから、母が父に相談したい時、父は母が言いたいことを理解するのに苦労します。母は理解してくれなくて怒り、父は理解できなくて怒ります。そんな時は両方の立場を理解できる僕がメッセンジャーになり、ケンカを防ぐ役割でした。例えば、父は苦手な日本食が多いので母が一生懸命に久しぶりの和食を作っても「これは不味い、これは食べられない」と言い、母ががっかりして、僕がなぐさめて父を注意することが何回もありました。今僕はもうドイツにいないので親が平和に暮らしているか心配です。
2つ目は日独の集団と個人の関係です。日本では集団主義が重視され、成功も失敗も全員ですると考えます。特に仕事では同僚に迷惑をかけたらだめ、足をひっぱるのはだめ、と思っているのではないでしょうか?自分よりグループに注目し全員でやればできると考えます。ドイツでは反対です。学校では自分はどう思う、自分で頑張ればなんでも出来る、いわゆる個人主義が広がっていると思います。ドイツでは自分の意見を持つこと、自分の意見を他の人に伝えることを学校で何回もディスカッションとかで練習させられました。ドイツと日本のハーフとして僕は両方の考えを意識しています。状況により集団主義または個人主義を意識し判断をしています。
3つ目は家族の捉え方です。日本では家族は親と子供だけではなく、祖父母も含まれる時が多いです。全員が同じ家か近くに住むのは特に数年前まで多かったと思います。子供も他の町の大学に行かなければ実家に住むのは当たり前だと思われています。しかし、ドイツでは18歳で家を出るのは結構普通です。「大学ではやっと一人暮らしが出来る」と楽しみにする子供がたくさんいます。または祖父母は祖父母の家、親は親の家、子供は子供の家に普通だったら住みます。それに、高齢者は家族が世話できなくなったら老人ホームに入ります。ドイツでは自分で新しい家族を作ることの方が大事です。親や祖父母も大事にしますが、「自分の家族は誰?」と聞かれるとドイツ人はほぼ全員が「妻と子供たち」と答えると思います。日本では家族は自分を育ててくれた親や祖父母ではないでしょうか?
国々はそれぞれの文化、メンタリティーや人間の考え方があり、比較すると色んな相違点があります。ドイツと日本のハーフとして2つの文化を経験しながら育ちました。一つの文化の生き方が正しいとは思いません。僕は日本人でもなくドイツ人でもないけど僕は自分のふるさとと言える国がないわけではありません。僕はふるさとを2つも持っています。こうして、2つのアイデンティティを持った僕は他の文化も理解しやすいと思います。2つの文化を紹介してくれた親に「世界中に色々な人々、考え方、メンタリティーが存在して、それぞれに存在価値があることを認めることが大切だ」と教えてくれて本当に感謝しています。
講評
永井 幸寿 会 長
海都さん,キンさん,ソフィアさん,ありがとうございました。
海都さんは,日本とドイツについて,表現の仕方,個人と集団の関係,家族のあり方についての違いをわかりやすく伝えてくれました。2つのアイデンティティがあると言っています。帰国子女などで,アイデンティティがどこにあるのかと不安になる人もいる中で,堂々とした優れた考えだと思います。また,日独のそれぞれが正しいと,それぞれを理解して,一方が優れているとしない見方は大変素晴らしいと思いました。
キンさんの長女がしっかりしなければならないという話は,日本にもある習慣で,これに喜び,負担になり,不信感,これを克服しようという話。私たちにも通じる話でした。更に,日本に来て,日本も似ているのかどうか,また,克服の過程についても機会があったらお話しいただければと思います。
ソフィアさんは,運と縁の話をしました。運は人がどうしようもないこと,縁は人と人とのつながりです。そして,アルゼンチンのこと,日本での活動を話しました。そして,運で日本に来てコロナで滞在が長引き,縁で人の色々な交わりがあったと言うことです。よくまとめたなと思います。また,言葉の勉強は,単に単語を覚えて,発音の練習をするだけでなく,言葉を使っている人たちの日常や文化等を知ることでより深く知れるのだと教えてくれました。
今,ロシアがウクライナを侵略しています。世界から戦争をなくして平和にする為にはどうすれば良いのでしょう。
軍隊を強くすることでしょうか。原子爆弾を持つことでしょうか。
国際RCはそういう考えは採っていません。国際ロータリーは,世界の人が異文化交流を通じて相互理解をはかり,紛争を解決するスキルを身につけた人材育成を通じて世界の平和に貢献しています。スキルを身につけた人が,国際連合のような国際機関や,政府や,NGOに入って活動しています。
異文化の理解の為には海都さんの言う様に,どちらも正しいという視点で相手を理解することが必要です。お互いに信頼しあい,協力すること,よりよい社会をつくることになります。
皆さんは,まだ,若いうちに,よその国に来て,色々な人と接する機会を持ちました。これから,世界が相互に理解し,協力し合う,平和な社会になるために,貢献してくれるものと思います。期待しています。
出席報告
☆ 出席担当委員
5月17日の出席者 25名(ZOOM出席2名を含む)
5月10日の出席者 24名
4月26日の出席者 23名(メークアップ1名を含む)
委員会報告
☆藤定 真由美 米山記念奨学会委員
ガバナー事務所より 米山寄付奨学会への寄付に関してのお願いが来ております。
「米山記念奨学事業におきましては、年度の寄付額に応じて、地区の奨学生採用人数が決定されることになります。多くのロータリアンの皆様にご寄付を頂いておりますことに、深く感謝申し上げます。しかしながら、昨年秋の米山月間の奨学生卓話派遣の中止やクラブ例会の取りやめなどの影響もあって、本年度当地区の寄付額は例年を大きく下回っております。クラブ事務局で米山Boxなどの預かり金がある場合は、6月末までに送金頂きます様にお願い致します。特別寄付へのご協力を賜れば幸いでございます。」
☆松本 考史 親睦活動委員長
紀伊国谷隆さんをしのぶ会を6月17日金曜日に開催します。
ニコニコ箱
☆藤定 真由美 副SAA
永井幸寿 さん 西クラブ様31人もお越し頂きありがとうございます。
奥田祐司 さん 神戸西クラブとの合同例会を祝して 本日のスピーチにコミュニカとYMCAの留学生を連れてきました。宜しくお願いします。
山本裕一郎 さん 神戸西RCの皆様 本日はよろしくお願いいたします
平山一哉 さん 西クラブの皆様 ようこそ
中橋康行 さん 神戸西クラブの皆様ようこそ神戸中クラブに!
岩﨑重曉 さん 久し振りの合同例会たのしいなぁー
大谷秀明 さん 神戸西RCの皆様 ようこそ神戸中RCへ
例会予定
☆2022年 6月 7日(火)第1366回 例会
「 会員卓話 」
当 番 髙橋 玲比古 会員
☆2022年 6月14日(火)第1367回 例会
「 委員会報告 Ⅰ 」
当 番 各委員会委員長
☆2022年 6月21日(火)第1368回 例会
「 委員会報告 Ⅱ 」
当 番 各委員会委員長
☆2022年 6月28日(火)第1369回 例会
「 四役退任挨拶 」
当 番 会 長 永井 幸寿 会員
副会長 奥田 祐司 会員
SAA 髙井 敏郎 会員
幹 事 山本 裕一郎 会員
本日のRCソング・BGM
☆ロータリーソング
「 上を向いて歩こう 」
☆BGM
「 A Whole New World 」「 My One And Only Love 」
「 この素晴らしき世界 」
ピアノ演奏 森田 純子 先生
山﨑弘子 副幹事 yamazaki-law@eagle.ocn.ne.jp