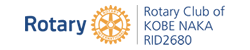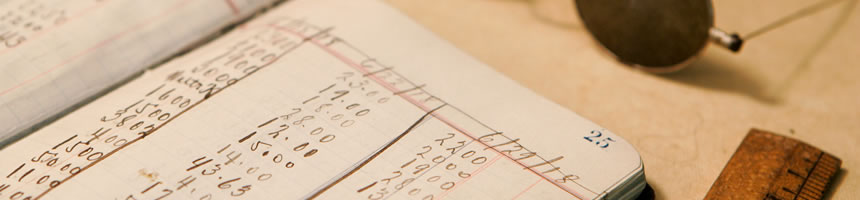
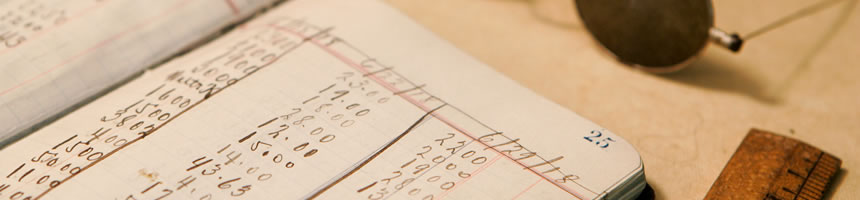
No.19 2022年11月15日号
今週の内容
☆2022年 11月 29日(火)第1389回 ハイブリット例会
「 南アフリカ紀行 」
スピーチ 平山 一哉 会員
当 番 國田 正博 会員
次週予定
☆2022年 12月 6日(火)移動例会のため 休会
12月 9日(金)「神戸西ロータリークラブと合同例会」に移動
前週の報告①
☆2022年 11月 15日(火)第1388回 例会
「 日本の感性が世界を変える 」
当 番 奥田 祐司 会員
司 会 副SAA 細谷 眞弓 会員
点 鐘 会 長 茂木立 仁 会員
前週の報告②
☆11月15日のRCソング・BGM ピアノ演奏 森田 純子 さん
ロータリーソング
「もみじ」
☆ソングリーダー 親睦委員 加藤 有加里 会員
BGM
「Someday My Prince Will Come」 「Triste Coeur」 「Etude I」
会長報告
☆会長 茂木立 仁 会員
ロータリーとは、という問いかけに対する様々な先輩方の言葉が集められているのを見つけました。ロータリー情報研究会 大西省司(福知山西南ロータリークラブ所属)からの引用です。
ポール・ハリス…「古くから存する道徳観念を現代社会に実践しようとするものである」
ハーバート・テイラー…「ロータリーは親交を作るものであり、人を作るものである」
ハロルド・トーマス…「己の欲せざる所を人に施す勿れ、という道徳観念である」
私は、えん(円、縁、宴)だと思っています。
ただ、それぞれ考えて、いろいろな方々の言葉を参考にして、自らの答えを見つけてみたらどうでしょうか。
幹事報告
☆幹事 山﨑 弘子 会員1.次週、11月22日(火)は定款の規定により休会となります。
2.12月6日(火)の例会は、12月9日(金)12時30分に移動し、神戸西RCとの合同例会となります。出欠をまだお知らせいただいていない方は、早急に事務局または幹事にお知らせください。
3.地区ガバナー事務所より、「財団室NEWS11月号ができました、地区ホームページから閲覧可能です」との連絡がありました。
以上
卓話
「 日本の感性が世界を変える 」当 番 奥田 祐司 会員
◎やわらか、あいまい、情熱的。今こそ、日本文明の出番だ!
1)日本の感性が世界を変える​
タタミゼ(tatamiser フランス語の動詞)効果について​
➡日本語を学ぶことでタタミゼ化した外国人学習者が心地よいと感じ、闘争的対立的な感覚が和らいで、礼儀正しくなり、控えめになり、婉曲な表現を使う、にこやかに謝ってしまう、人にも優しくなったと感じていること。それが今世界平和に大きく役立っている。今まさに西欧のキリスト教的世界観(人間至上主義が生態系や自然環境の破壊を生み出した)から日本的な文明(アニミズム的で汎神論的な世界観)への転換を図る時期である。​
アニミズム:生物・無機物を問わない全てのものの中に霊魂、もしくは霊が宿っているという考え。​
汎神論:神と宇宙、または神と自然とは同一であるとみなす哲学的・宗教的立場である。​
2)日本語は世界で唯一のテレビ型言語​
◎1)日本の感性が世界を変える(タタミゼ効果について)
タタミゼ(tatamiser)効果とは?​
タタミゼとは元々フランス語で使われた新しい言葉で、(フランス人が)日本かぶれする、日本びいきになる、日本人ぽくなる、といった意味である。アルセーヌ・ルパンの時代から柔道が盛んな国だけあって畳が日本のシンボルとして使われているらしい。​
以前から日本語研究者・日本語教師・日本語学習者の間では、「日本語を学ぶと性格が穏和になる」「人との接し方が柔らかくなる」ということが指摘されていた。日本語の持つこうした「人を優しくする力」に着目して、鈴木孝夫先生は「タタミゼ効果」と名付けた。「日本語、日本文化というのは悪く言えば人を軟弱にする、良く言えば喧嘩とか対立、対決が出来にくい平和的な人間にしてしまいがち」だというのだ。米国の文化人類学者エドワード・ホールは世界中の言語を高文脈文化(言葉として表現された内容よりも言葉にされていないのに理解される内容の方が豊かな伝達方式)と低文脈文化(言葉に表現された内容のみが情報としての意味を持ち、言葉になっていない内容は伝わらない)に分類し、日本語は最も高文脈文化の特徴がある。日本語教師が外国人に日本語を教える時は音や文法だけではなく、日本語が高文脈言語であることも教える。​
*鈴木孝夫著「日本の感性が世界を変える」新潮選書より​
◎タタミゼ効果の実例
①元在日ロシア大使館一等書記官文化担当官 セルゲイ・ハルラモフ氏の場合​
東海大学での柔道の練習が日本の理解を深めるのに大いに役立った。武道場での雰囲気は​
日本社会の構造・文化・伝統を反映している。伝統や年上の人に対する尊敬の心、先輩と自分との関係、​
厳しい規律、そして何よりもルールを守らなければならないということ。何か決まったら、他の動きは出来なくなり、変更はあり得ない。また日本人は自分のことだけではなく、周りにもとても気を遣う。​
➡モスクワに帰った時に「日本人になったみたいだ」と冗談で言われるくらい、自分でも日本人に近くなった気がする。その理由は,「人当たりが柔らかくなった」「柔軟な態度」「否定したいときの答え方が、いいえ、ではなく検討しますと言うようになった」等​
*ただし、外国の人が日本に来て何年か日本語を習ったり、長期に渡って日本に滞在したりすれば、皆がみなそうなる訳ではないのは勿論です。その人の持って生まれた性格・職場の環境・どのような友人関係を​
持ったか等、様々な要因が複雑に絡んでいます。
◎タタミゼ効果の実例(コミュニカ学院留学生からの報告)​
①あいづち・うなづきながら聞く習慣(韓国・台湾の男女)​
何でも賛成して、自分の意見が無いのかと両親に言われた。相手の話をうなづきながら聞く習慣が身に付いていた。あいづちを打たない相手には、母語の会話で聞いてる?と言ってしまう。うなづくことは、相手への気遣い、優しさだと思う。​
②よく謝るようになった(国籍不特定)​
話をゴメンねから始める。​
③人の話を聞くようになった・自分だけ話さない(フランス女性)​
一時帰国したときに友人から静かになったと言われた。相手の話をよく聞くようになった事に気付いた。フランス語で会話していると話があちこちに飛んで疲れる。断定しなくなった。​
​
◎タタミゼ効果の実例(コミュニカ学院留学生からの報告)
はっきり言わない。文脈・行間に意味を込める(フランス男性)​
自分の英語が変わってきた。ストレートに言わなくなった。以前は日本人の英語は、表面的な言語上の意味は分かるが、意図が全く理解出来なかった(婉曲な断りなど。例として、あるプロジェクトでパートナー企業の日本人担当者から「これこれしかじかの状況で、これこれが、難しい」と言われたが、「良く分かりました。それで、いつ完成しますか?」と反応していた。それが気付いたら、自分の英語でのやり取りもハイコンテクスト、行間依存になっていた。相手によって今は英語を使い分けている。​
⑤とりあえず(韓国男性)​
物事は計画を立てて、見通しをつけてからやるのが正しいと教えられたし、そうしてきた。先ずやってみて、その経験から何かを始めることはなかったが、日本語の「とりあえず」 という言葉に出会ってから、「とりあえず」始めることの大切さを知り、自分の社会との関わり方や感じ方、行動が変わった。​
​自分に対して悔しい(韓国女性)​
韓国語では相手の行動によって自分が不利益を被った時にしか「悔しい」と言わない。韓国語で自分の行動が悔しい対象にならないため、自分の行動に対して「悔しい」という感覚が分からなかった。日本語が上達につれて、自分の行動が自分に返ってくることが良く分かるようになった。きちんと出来なかった自分を反省する「悔しい」は日本語でしか言えない。​
⑦無防備になった(国籍不特定)​
国に戻ると無防備になっている自分に気付いた。置き引きに合う。財布をすられる。販売機に商品の金額以上の釣銭が必要な紙幣をいれてしまう。レストランの請求伝票をチェックしないで、注文以上の金額を払わされた。タクシーのドアが開くのを待っていて、後ろから来た人に先に乗られてしまった。​
⑧食器を片付ける(台湾女性)​
セルフスタイルのレストランで、食後にトレーで食器を返却口まで返した時、母に日本に行ってメイドになって帰ってきたと言われた。台湾は協力したり次のお客のことを考えたりしない文化だと思った。日本スタイルの方が気持ちがいい。​
⑨日本に帰るとホットする(国籍不特定)​
言葉(声調、音声、物言い)の柔らかさがある。優しい。直接的に言わない。人を押しのけて競争することがない。始まりの時間は厳しいが、終わりの時間は緩やか。​
⑩おかげさまで(スペイン女性)​
スペイン語を話しているにもかかわらず、思わず「おかげさまで」という日本語が口をつく。​
​
◎日本が世界を変えた実例
①日本人が世界に対して行ったマニュフェスト​
第一次世界大戦終了後の国際連盟の設立委員会において「あらゆる人種差別の撤廃を求める人種平等案の採択」を強硬に主張。アメリカ・イギリス・フランスの反対によって採択されなかった。その背景には当時イギリスはアパルトヘイト政策を南アフリカで、オーストラリアでは白豪主義を、アメリカでは黒人差別を、フランスでは植民地政策が行われていた。​
次に大東亜戦争の開戦理由としては自衛の戦争に加えて、白人国家による有色人種の植民地支配を終わらせることがあった。日本によって解放されたアジア地域の6つの国(満州国・中華民国・フィリピン・タイ・インド・ビルマ)を東京に呼び、東条英機首相を議長として1943年11月5-6日に大東亜会議が開催された。その席上、広く前記の事を世界に宣言した。​
日本の敗戦後、アジア・アフリカ・オセアニアでは植民地の独立ラッシュが起こった。アフリカ大陸には54の独立国が生まれ、アジアではインド・スリランカ(セイロン)・パキスタン・ミャンマー(ビルマ)・​
​マレーシア・インドネシア・フィリピンなど46ヵ国、オセアニアでは12もの新しい有色人種の独立国が誕生した。西欧諸国は戦争には勝ったが、この戦争で有色人種である日本人が示した強さと、植民地解放に対する熱意を現地の人々が目の当たりにしたために、西欧諸国の絶対的な権威が地に落ちたため、押さえが利かなくなったのが要因と考えられる。​
(例)​
・インドネシア(旧称東インド)の独立​
オランダは17世紀初頭から350年間植民地支配をしてきたが、日本によって解放されたこの地域を日本の降伏後再び元の植民地状態に戻すために、直ちに軍隊を送り込んだ。独立のために立ち上がったインドネシア解放軍は、自らの意思で残った2千名もの旧日本兵たちの指導支援を受けながら、オランダ軍と約5年近くも戦い、80万人近いインドネシア人犠牲者がでました。その後渋々停戦に応じたオランダは謝罪して賠償金を支払うどころか、60億ドルを要求した。​
​
◎日本語はテレビ型言語​
​ 日本語はテレビ型言語(大脳の二箇所、音声処理と映像処理を同時に使いながら処理する)で、ヨーロッパ語などはラジオ型言語に分類されます。日本語は同音で意味の違う言葉が多いので、耳で聞くだけでは意味の良く通らない場合があります。例えば「けいやくのこうかい」と聞いても更改なのか公開なのか分かりにくい。「ふねはこうかいにでた」の「こうかい」も公海か黄海か紅海か航海か分からない。アクセントとか、文脈でも分からない。カタカナや音声だけの表示では理解するのに苦労する。それが、漢字が使われれば、意味の理解がずっと楽になります。漢字が使われると、文字が音声を表現するだけではなく、意味を表すので、眼による意味の理解と音声による理解が同時に出来るからです。日本語は、話を聞いているときに、単語がどんな漢字で表記されているかという知識がないと、意味が分からなかったり、取り違えたりします。漢字の知識によって、眼と耳による理解が成り立つのでテレビ型言語だとしています。これに対し、ヨーロッパの言語は表音文字で書かれているので、音声による理解なのでラジオ型言語と言えます。現在世界では約6千種もの多様な言語が用いられているが、全てラジオ型言語に分類される。ラジオ型言語は音の中に全ての必要な情報が含まれているので、文字が無くても互いの伝達には支障がない。そのことが識字率にも大きく関係している。​
​◎日本語放棄論​
日本語は人間の言葉として出来の悪い欠陥言語であるから、これをもっと効率の良い西洋の言葉を国語として採用しなければ、西洋の文明から取り残されるとした考え日本​
1)初代文部大臣 森 有礼(モリ アリノリ) 「英語為邦語之論」→英語を国語にしようとした、但しその英語には時制も活用もない​
急進的な欧米主義者で最後は国粋主義者によって暗殺される。日本の欧米による植民地化を防ぐために行ったとも言われている。​
・2)志賀直哉 →昭和21年雑誌「改造」に「国語問題」と題する文章を掲載​
日本が愚かな戦争をして惨めな結果となった原因は日本語の不完全さと不便さ、漢字学習の効率の悪さのせいとした。敗戦を機に​
フランス語を国語にすべきと提案した。​
3)尾崎行雄〈咢堂〉→政治家で憲政の神様と称される人物で文部大臣経験者​
日本語という幽霊を退治し、非能率な漢字を追放しなければ日本の民主化は望めないと主張。日本語廃止運動の賛同者を求めて​
アメリカにまで行く。​
(日本以外)どの国民も自分たちの母語に対しては絶大の信頼と愛情を寄せ、国語の持つ美しさを歌い上げる詩人文学者には事欠かない
​
出席報告
☆出席担当 髙井 敏郎 会員
11月15日 出席者 26名(ZOOM 2名を含む)
11月 8日 出席者 23名(ZOOM 2名を含む)
11月 1日 出席者 24名(ZOOM 2名を含む)
委員会報告
☆なかよし会 大谷秀明 会員
ゴルフ同好会 なかよし会「第 120 回記念大会」開催
12月8日(木)@美奈木ゴルフ倶楽部
表彰懇親会 18:00~ @イタリアン 『 ドンナロイア 』
☆RID2680インターアクト小委員長 大谷秀明会員
第 38 回インターアクト地区年次大会開催
2022 年 11 月 23 日(水・祝)10:30 @ネスタリゾート神戸
その他の報告
ニコニコ箱
☆副SAA代理 髙井 敏郎 会員
茂木立仁 さん 寒くなりました。皆様、御身体お気を付け下さい。
山﨑弘子 さん 皆様 コロナ感染に気をつけましょう。
例会予定
例会予定
☆2022年 12月 6日(火)移動例会のため 休会
12月 9日(金)「神戸西ロータリークラブと合同例会」に移動
☆2022年 12月 9日(金)第1390回移動例会
「神戸西ロータリークラブとの合同例会」
☆2022年 12月 13日(火)第1391回 例会
「 新入会員自己紹介 」 当 番 前原 義浩 会員
☆2022年 12月 20日(火)移動例会のため 休会
12月 23日(金)「クリスマス家族会」に移動
☆2022年 12月 23日(金)第1392回 移動例会
「 クリスマス家族会 」 当 番 親睦活動委員会
☆2022年 12月 27日(火)定款により休会
本日のRCソング・BGM
☆11月29日のRCソング・BGM ピアノ演奏 森田 純子 さん
ロータリーソング
「たきび」
BGM
「Colors Of The Wind」 「Madrigale」 「Home On The Range」
藤定真由美 副幹事 mau@maunatural.com